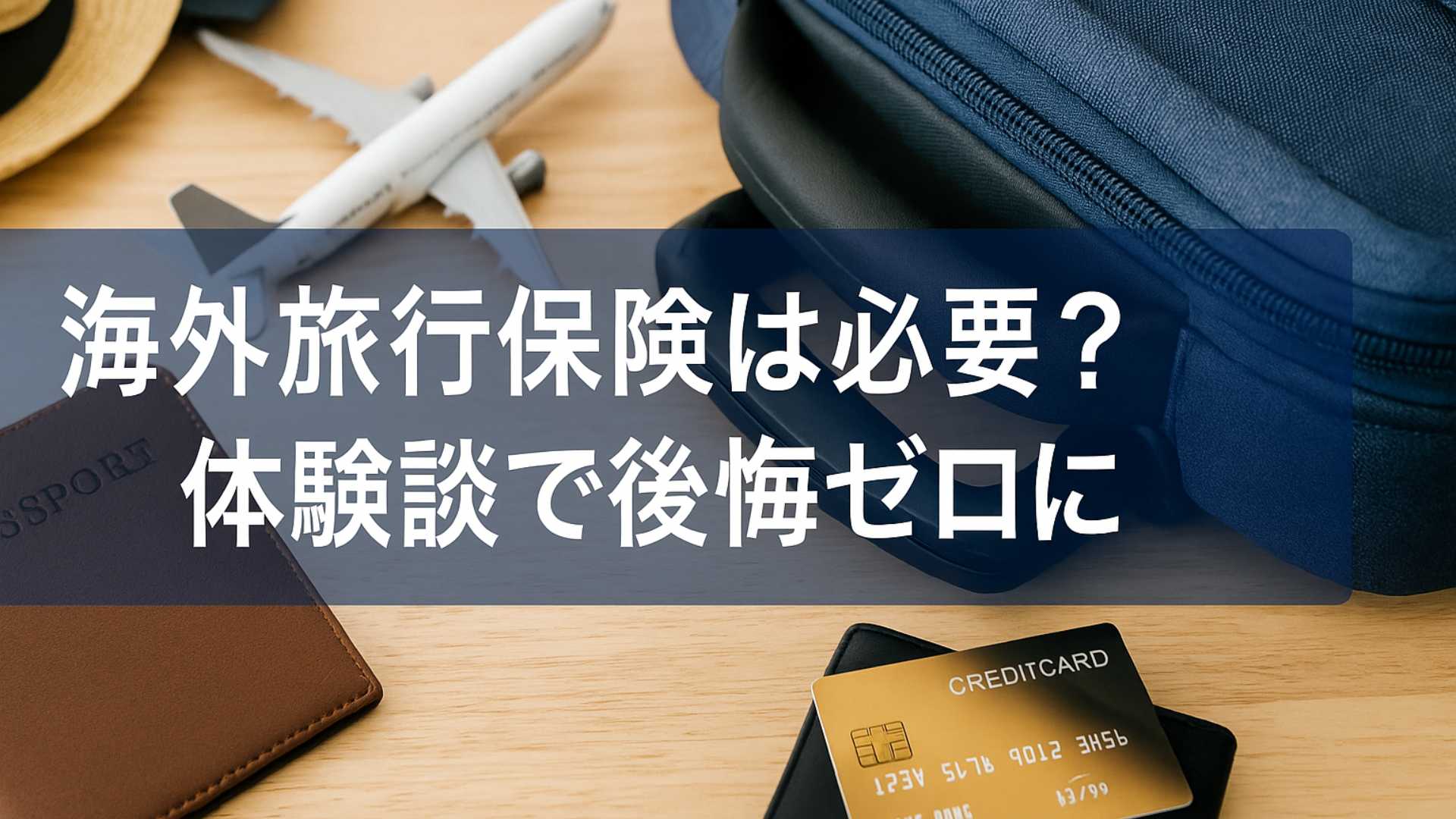「海外旅行保険って、本当に必要なの?」
そんな疑問、誰もが一度は感じたことがあるはず。
実際に保険に入らず数十万円の治療費を請求された人や、入っていたおかげで通訳付きで安心して治療を受けられた人もいます。
この記事では、リアルな体験談や補償内容、保険の選び方までわかりやすく解説。後悔しない旅の備え、ここから始めませんか?
- 海外旅行保険が本当に必要な理由とリスクを実例つきで解説
- クレジットカード付帯保険との違いや補償の落とし穴も網羅
- 自分に合った保険の選び方とネットで安く加入する方法も紹介

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
そもそも海外旅行保険は本当に必要?
これから「海外旅行保険に加入しないとどうなる?補償されない主なリスク」について解説します。
医療費が高額な国では一晩の入院で数十万円
海外では、ちょっとしたケガや病気でも驚くほど高額な医療費がかかります。
特にアメリカやヨーロッパなどの医療費が高い地域では、一晩の入院だけでも数十万円から、場合によっては100万円を超えることもあります。
日本のように国民皆保険制度がある国は稀で、海外では医療費は全額自己負担が基本。
厚生労働省や外務省のデータでも、海外旅行先での医療費トラブルは毎年数多く報告されています。
ニューヨークで腹痛を訴え、現地の病院で検査を受けたケースでは、わずか数時間の診療で約40万円の請求があったという事例もあります。
さらに、入院や手術が必要になると、その金額はあっという間に3桁に届きます。
保険に入っていれば、こうした出費をすべてカバーしてもらえる可能性が高くなります。
海外旅行を安心して楽しむためにも、医療費のリスクは見逃せません。
トラブル時に日本語サポートが受けられない不安
言葉が通じない海外でのトラブルは、想像以上にストレスになります。
医療機関での説明や書類のやりとり、警察への対応など、すべて現地の言語で対応しなければならないことも珍しくありません。
旅行保険に加入していない場合、日本語の通訳や緊急支援サービスが利用できず、自力での対応を求められることになります。
特に体調が悪い時やパニックになっているときには、冷静に対処するのは困難です。
パリでひったくりに遭った旅行者が、警察での被害届を英語でなんとか伝えようとしたものの、内容がうまく伝わらず証明書をもらえなかった…という話もよく耳にします。
その結果、保険請求ができなかったというケースも。
保険に入っていれば、24時間対応の日本語サポートデスクがついており、現地とのやり取りやトラブル処理をサポートしてくれるのは大きな安心材料になります。
救援者渡航費用・遺体搬送費用などが自腹になるケース
万が一の事態に備えるのも、海外旅行保険の大切な役割のひとつです。
事故や重病などで家族が現地に駆けつける必要がある場合、その渡航費や滞在費は、保険に入っていないとすべて自己負担になります。
外務省のデータによると、海外で日本人旅行者が事故や急病により死亡するケースも年に数百件あり、遺体搬送費用として100万円を超える請求が発生することもあります。
タイでのバイク事故で亡くなった日本人旅行者のケースでは、遺体を日本へ搬送するためにかかった費用が約150万円。
そのすべてを遺族が自費で支払うことになったという実例もあります。
こうした「起こらないでほしいけど、ゼロではないリスク」に備えるのが、保険の役割です。
費用面だけでなく、精神的な負担も軽減できるため、万が一に備えたい方には特におすすめです。
世界の医療費は想像以上?実際のトラブル事例で解説
これから、海外での医療費がどれほど高額になりうるかを、実際のトラブル事例とあわせて解説します。
実際のケースは下記のようなケースがあります。
- アメリカで虫垂炎治療→300万円の請求
- パリで骨折→手術・滞在費込みで200万円超
- 現地でのキャッシュレス診療の有無で全然違う安心感
それでは一つずつ解説します。
アメリカで虫垂炎治療→300万円の請求
まずは「アメリカでの医療費がどれほど高額なのか」について解説します。
アメリカは世界でも特に医療費が高い国のひとつで、保険なしでの治療は非常に大きなリスクになります。
軽度の処置でさえ数十万円かかることも多く、入院や手術が必要な場合には一気に数百万円単位の出費になることも。
厚生労働省「海外での医療事情」によると、アメリカでの虫垂炎の治療にかかる費用は、一般的に$15,000〜$30,000(日本円で約230〜460万円 ※為替により変動)とされています。
これは検査、入院、手術、術後のケアなどを含めた金額です。
ロサンゼルスを旅行中だった日本人女性が、急な腹痛で病院を受診し、虫垂炎と診断され緊急手術。
その結果、3日間の入院と手術で約300万円の請求を受けたというケースがありました。
幸い、事前に保険に加入していたため全額補償され、大きな負担を避けることができたそうです。
アメリカでは「高額医療」が当たり前の環境です。保険なしで渡航することは、まさに経済的ロシアンルーレットと言っても過言ではありません。
パリで骨折→手術・滞在費込みで200万円超
ヨーロッパの中でもフランスやドイツなどは医療体制が整っている反面、旅行者にとっては「保険適用外」であるため、費用は非常に高額になりがちです。
加えて、入院に伴う滞在費や生活費も大きな負担となります。
フランス保健省のデータによると、非居住者の骨折治療では1回の手術+5日間の入院で€10,000(約160万円)以上が請求されるケースもあります。
これにホテル滞在や家族のサポート費用が加わると、簡単に200万円を超えてしまいます。
実際、パリ旅行中に階段で足を滑らせて足首を骨折した日本人男性が、現地の公立病院で即日手術。
その後、入院期間延長により10日間の滞在を余儀なくされ、医療費と滞在費を合わせて約220万円の請求を受けたそうです。
こちらも旅行保険による全額補償で経済的な打撃を回避できたとのこと。
ヨーロッパだから安心…と思っていると、いざという時に想定外の出費に直面する可能性があります。
現地でのキャッシュレス診療の有無で全然違う安心感
「キャッシュレス診療があるかどうかでどれだけ安心感が変わるか」について解説します。
海外で医療を受ける際、保険にキャッシュレス対応があるかどうかは大きな違いです。
キャッシュレス診療が利用できる保険であれば、現地での支払いが不要なため、言葉の不安や高額な支出を気にせず治療を受けることができます。
外務省・海外安全ホームページでも「キャッシュレス診療は安心して医療を受けるための重要な要素」として紹介されており、対応病院の一覧や手続き方法も案内されています。
バンコクで体調不良を訴えた旅行者が、キャッシュレス対応病院を紹介されて受診。
パスポートと保険証を提示するだけで診察・処方・血液検査まで完了し、その場での支払いはゼロ。
通訳サポートもあり、非常にスムーズだったと語っています。
一方、同じタイで現金払いが必要なクリニックを訪れた別の旅行者は、手持ちの現金では足りず、クレジットカードも使えずに大変な思いをしたとのこと。
保険の加入だけでなく、「どの保険を選ぶか」が旅の安心感を大きく左右します。
クレジットカード付帯保険で本当に足りる?
クレジットカードに付帯している海外旅行保険の仕組みや注意点について解説します。
- 自動付帯と利用付帯の違いとは?
- 補償額・補償範囲の落とし穴と注意点
それでは一つずつ解説します。
自動付帯と利用付帯の違いとは?
「何もしなくても保険が効く」のはどっち?
旅行に出発するだけで保険が有効になるのが「自動付帯」、一方で旅行代金や航空券などをカード決済したときにのみ保険が適用されるのが「利用付帯」です。
手間のなさでは自動付帯が優れていますが、利用付帯の方が補償内容が手厚いカードも少なくありません。
大手カード会社の多くは、ゴールドカード以上で自動付帯が主流ですが、年会費無料のカードは利用付帯が多い傾向にあります。
たとえばJCBや楽天カードでは、種類によって付帯条件が大きく異なります。
関空からタイに出発したAさんは、「カード持ってるから大丈夫」と思っていたものの、実は利用付帯タイプで、旅行代金を別の決済方法で支払っていたため、保険が適用されずに実費負担となりました。
保険が“勝手についてくる”と思っていると落とし穴にはまる可能性があります。
カードによって条件は異なるため、出発前にしっかり確認することが大切です。
実は“自動付帯”でも条件があることも
自動付帯と聞くと、旅行に行けば必ず保険が使えると思いがちですが、じつは細かい条件が設定されていることもあります。
中には「出国後〇日以内のみ」「短期旅行に限る」といった制限が設けられていることもあります。
JALカードや三井住友カードの一部プランでは、自動付帯であっても補償開始が「日本出国日から90日間」などに限定されています。また、キャッシュレス診療に対応していないケースも多く、緊急時の不安要素になり得ます。
ハワイで病気になったBさんは、自動付帯のカードを持っていたにもかかわらず、出国から3ヶ月以上経過していたため補償対象外に。結果として、高額な医療費を負担することになってしまいました。
“自動”という言葉に安心しすぎるのは危険です。
カードごとの詳細な補償期間・対象条件を必ずチェックしておきましょう。
付帯条件を満たさず保険が無効になる失敗例
利用付帯のクレジットカードでは、旅行関連の費用をカードで支払っていないと、保険がまったく適用されないというケースがあります。
これに気づかず「保険があるから大丈夫」と油断している人は少なくありません。
とくに交通費・ツアー代金など、「どの支払いに使えばOKか」はカード会社によって異なります。VisaやMastercardなどブランドではなく、カード発行元の規定をよく確認することが必要です。
韓国旅行に行ったCさんは、航空券を予約サイトで別のクレカ決済していたため、付帯保険の対象外に。現地でケガをして病院にかかるも、自分のカード保険が無効であることが現地で発覚し、治療費約12万円を全額負担する羽目になりました。
保険を「ついてるもの」と思い込まず、使える状態になっているかを事前に確認しておくことが、万が一の時の安心につながります。
補償額・補償範囲の落とし穴と注意点
医療費の補償額が100万円未満では危険?
多くのクレジットカード付帯保険では、医療費の補償上限が100万円前後に設定されています。
しかし、前章でも紹介したように、アメリカやヨーロッパでの治療費は数百万円にのぼるケースもあり、100万円では到底カバーしきれません。
損保ジャパンの調査によると、海外で入院・手術が必要になった場合、平均治療費は約200万~300万円前後。100万円の補償では不十分なのが現実です。
ニューヨークで虫垂炎を患ったDさんは、300万円の医療費がかかったものの、カードの補償は100万円まで。差額の200万円を自己負担することになり、帰国後もしばらく支払いに苦しむ結果となりました。
金額だけで「保険がある」と安心するのは危険です。必要な補償が受けられるかを冷静に見極めることが重要です。
航空機遅延・携行品損害は対象外なことも
カード付帯の海外旅行保険には、そもそも“対象外”の項目があることもあります。
よくあるのが、航空機遅延やロストバゲージ(手荷物遅延・紛失)、携行品の破損・盗難などが補償されないケースです。
エポスカードの一般プランでは、こうした「旅のトラブル系」の補償は基本的に対象外。
ゴールドやプラチナなど、上位カードでようやく一部補償されるといった構造になっています。
成田発の便が欠航し、1泊ホテルに滞在せざるを得なくなったEさんは、カード付帯保険では補償されず、自腹で2万円以上の出費に。携行品の盗難にも対応しておらず、保険の意味が感じられなかったと話します。
カード保険の「対象項目」を知らずに過信してしまうと、トラブル時に後悔することになります。事前に補償範囲を比較することが肝心です。
カード会社により補償内容が大きく異なる
一口に“クレジットカード付帯保険”といっても、補償金額・範囲・付帯条件はカード会社ごとにまったく異なります。
とくに無料カードと有料カードでは差が大きく、内容を確認せずに「どれも同じだろう」と思っていると痛い目を見ることも。
| カード名 | 傷害治療補償 | 疾病治療補償 | 携行品損害 | 自動/利用 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 200万円 | 200万円 | 20万円 | 利用付帯 |
| エポスカード | 270万円 | 270万円 | 20万円 | 自動付帯 |
| 三井住友カードNL | 50万円 | 50万円 | 15万円 | 利用付帯 |
旅行中にケガをしたFさんは、三井住友NLカードの補償額が思ったよりも低く、治療費の多くを自己負担することに。保険の存在に安心しきっていたものの、補償内容の差に驚いたそうです。
カード保険は“おまけ”ではありますが、補償内容を精査すれば「使える保険」として安心感につながります。逆に、条件を知らずに頼るのは非常にリスクが高い行動といえるでしょう。
海外旅行保険がカバーする補償内容とは?
これから、海外旅行保険で実際にどのような補償が受けられるのかについて解説します。
- 3-1. 医療・救援・損害・賠償・盗難…何が含まれる?
- 3-2. 「キャンセル料」「携行品損害」は対象になる?
それでは一つずつ解説します。
医療・救援・損害・賠償・盗難…何が含まれる?
海外で病気・ケガをしたときの医療費補償
海外でのケガや病気による診療・入院・手術などにかかる費用は、旅行保険の基本ともいえる補償項目です。
多くの保険商品では、治療費に数百万円単位の補償がついており、国や地域に関係なく安心して医療機関を受診することができます。
損保ジャパンの調査では、海外での治療費の平均請求額は約230万円。
中でもアメリカ、カナダ、ドイツ、シンガポールなどは医療費が高額であり、補償がなければ非常に大きな経済的負担を強いられることになります。
シンガポールを訪れていた日本人女性が現地で感染症にかかり、5日間入院。医療費は総額で約180万円にのぼったものの、保険で全額補償されたため、支払いのストレスなく治療に専念できたと話しています。
医療費補償は「万が一」に備えるだけでなく、安心して旅先で行動するための土台になります。補償額の上限や自己負担の有無はしっかり確認しておきましょう。
家族が現地に駆けつけるための救援費用
重大な病気や事故で入院が長引いた場合、日本から家族が現地に駆けつける必要が出てくることもあります。
旅行保険では、そうした家族の渡航費・滞在費も「救援者費用」として補償されるケースが多くあります。
外務省の「海外邦人援護統計」では、毎年1,800件を超える日本人旅行者の医療・救援支援が発生しており、その多くが家族による現地対応を必要としています。
イタリアでバイク事故に遭った旅行者が集中治療を受けることになり、家族が現地に向かうことに。飛行機代と宿泊費で30万円以上かかりましたが、加入していた保険の救援費用補償で全額カバーされ、大きな助けになったそうです。
もしもの事態に「家族がすぐに来られる」体制を整えておくことは、本人にとっても家族にとっても安心につながります。
第三者への賠償責任や携行品の損害補償
旅行中の思わぬ事故で、他人にケガをさせたり物を壊してしまった場合、その損害を賠償しなければならないケースもあります。そんなときに役立つのが「個人賠償責任補償」です。
また、スマートフォンやスーツケースなど、持ち物が壊れたり盗まれたりした場合の「携行品損害」も保険でカバーされます。
東京海上日動の資料によると、旅行中に最も多いトラブルのひとつが「携行品の破損・盗難」で、全体の2割を占めています。
また、個人賠償は高額請求になるケースもあり、1件で数十万円〜百万円超になることもあります。
観光中に誤ってカフェの高級グラスを倒し、店内のスピーカーまで壊してしまった旅行者が、損害賠償を求められたという事例では、約40万円の請求が来ましたが、保険で全額補償されたことで問題にならずに済んだそうです。
他人に迷惑をかけたときも、自分の持ち物がトラブルに巻き込まれたときも、旅行保険があることで冷静に対応できます。
「キャンセル料」「携行品損害」は対象になる?
出発前のキャンセルでも保険が使える?
急な病気や不幸などで旅行をキャンセルせざるを得ないときに、事前に支払った旅行代金を補償してくれるのが「旅行キャンセル費用補償」です。
ただし、すべての保険商品でこの補償が含まれているわけではなく、特約として追加が必要な場合もあります。
大手旅行保険比較サイト「保険市場」によると、キャンセル補償は標準でついている保険は少なく、オプション加入率は全体の3割ほどにとどまっています。
発熱のためフライト前日にキャンセルせざるを得なかったGさんは、ツアー代金の8割を自己負担しなければならず、その金額は10万円以上に。キャンセル補償を付けていれば、これらはすべて保険対象になっていたとのことでした。
旅行前のトラブルも保険で守れるよう、出発前のアクシデントを想定した補償の有無をチェックしておきたいところです。
スマホやカメラの破損・盗難も対象に
旅行中のトラブルで多いのが、スマホやカメラの落下・破損・盗難です。これらを補償してくれるのが「携行品損害補償」です。
補償限度額は保険によって異なりますが、1つのアイテムにつき10万円前後が上限となっていることが一般的です。
エポスカードや損保ジャパンの海外旅行保険では、1事故につき10万円〜20万円程度までが補償範囲となっており、スマートフォン・カメラ・スーツケースなどが対象に含まれます。
ベトナムでスマートフォンを落下させて画面が全損したHさんは、保険会社に申請して9万円の補償を受けることができました。
修理不能のため新機種に買い替える費用をカバーできたと話しています。
大切なガジェット類を持ち歩く海外旅行では、携行品補償の存在が安心材料になります。
高額なものを持って行く場合は特に注意が必要です。
補償対象とならないケースの注意点
保険があるから大丈夫、と思っていても、いざというときに「対象外」と言われるケースは少なくありません。
旅行保険にも適用除外事項があり、誤解しやすい落とし穴のひとつです。
主な除外例には以下のようなケースが含まれます
- 故意または重大な過失による事故
- 飲酒・薬物使用中のトラブル
- 紛失(盗難ではなく、自己過失による置き忘れなど)
- 経年劣化や自然損耗による破損
台湾でカメラを置き忘れて紛失したIさんは、盗難ではなく「管理不十分による紛失」と判断され、保険金が支払われなかったとのこと。本人は盗まれたと考えていましたが、現地調査で“置き忘れ”と判明しました。
補償される内容だけでなく、「補償されない」条件も知っておくことで、無用なトラブルやショックを避けられます。
保険に入っていた人の実例と、入っていなかった人の後悔
これから、旅行保険に「入っていて良かった」人と「入っていなくて後悔した」人の実例について解説します。
- 4-1. 実際に使った人の体験談(救急搬送・盗難・入院など)
- 4-2. 加入しなかった人が帰国後に直面した問題
それでは一つずつ解説します。
実際に使った人の体験談(救急搬送・盗難・入院など)
ケガで即入院!キャッシュレス診療で助かった
海外での医療トラブルは、突然のケガや病気が多く、言葉やお金の問題が重なってパニックになりやすいです。
そんなときに「キャッシュレス診療」が利用できる保険に入っていたことで、救われたという声は少なくありません。
損保ジャパンの調査でも、海外旅行中の医療利用者のうち約60%がキャッシュレス診療を希望し、そのうち90%以上が「非常に助かった」と回答しています。
台湾でバイクに巻き込まれ、足を骨折した20代男性は、救急搬送のあと即入院。手術が必要となり、治療費は80万円を超えましたが、キャッシュレス対応の保険により現地での支払いはゼロ。日本語通訳も付き、本人も家族も安心して治療に専念できたと話しています。
体が動かせない、言葉が通じない、現金も下ろせない…そんな状況で保険がどれほど心強い存在か、体験して初めてわかるものです。
空港でスーツケース紛失→補償で新調できた
これから、空港でのトラブルと保険の補償についてご紹介します。
空港での手荷物紛失や遅延は意外と多く、旅行開始直後に気持ちが沈んでしまう原因のひとつです。こうしたトラブルに対しても、旅行保険には「携行品損害補償」や「手荷物遅延費用」がついていることがあり、衣類や生活用品の再購入費用が補填されます。
国土交通省の発表によると、国際線の手荷物遅延・紛失は年間約4万件。航空会社の対応だけでは足りないケースも多く、補償付き保険が活躍しています。
ハワイの空港でスーツケースが出てこなかった女性は、3日後にやっと荷物が見つかったものの、それまでの生活用品や衣類を現地で買い直すことに。合計で3万円以上の出費となりましたが、保険により全額が補償され、むしろ新しい服で観光を楽しめたと笑って話していました。
旅のスタートでつまずかないためにも、こうした細やかな補償のありがたさは見逃せません。
4-1-3. 子どもの高熱で現地通訳付き医療に救われた
これから、小さなお子さんとの旅行中に医療支援を受けたケースをご紹介します。
子連れ旅行では、体調不良が起こりやすいもの。特に小さな子どもが熱を出すと、現地の病院で説明したり処置を受けること自体が大きなストレスになります。そんなとき、日本語サポートがある旅行保険は、精神的にも実務的にも大きな助けになります。
海外邦人安全対策連絡協議会によると、未就学児の海外医療利用は年々増加傾向にあり、その多くが旅行保険を活用して受診しているとされています。
グアム旅行中、4歳の娘さんが急な発熱で夜間に現地病院を受診した家族は、電話1本で保険会社のサポートセンターに連絡。すぐに通訳付きの診療予約が取れ、キャッシュレスで受診できたため、焦らず冷静に対応できたとのことです。
特に子ども連れの旅行では、“安心の仕組み”がどれだけ整っているかが、旅の充実度を左右します。
加入しなかった人が帰国後に直面した問題
治療費数十万円をカードで分割払い…
「大丈夫だろう」「短期旅行だから問題ない」という油断から保険に入らず出発し、現地で病気やケガに見舞われてしまうと、すべての医療費を自己負担することになります。
結果として、数十万円の請求をクレジットカードで支払い、帰国後も家計を圧迫するケースが後を絶ちません。
厚労省のデータでは、海外旅行者の医療費自己負担額の平均は約30万円。
無保険のままではとても軽視できない金額です。
オーストラリアで食あたりにより入院した男性は、点滴と2泊の入院費用が約25万円。
保険に入っていなかったため、全額をカードで分割払いし、半年以上にわたり支払いが続いたといいます。
金銭的な負担が帰国後も続くことは、心にも大きな影響を与えます。
たった数千円の保険料で避けられた出費と考えると、やはり備えは大切です。
医療拒否・通訳不在で不安なまま帰国
保険に加入していないと、医療機関によっては「支払い能力が確認できない」として診療を断られることもあります。
さらに、通訳がいない病院では、症状の説明や同意書のサインも自力で対応する必要があり、正確な処置を受けられないリスクも高まります。
実際に外務省が発表した資料にも、現地の病院でのトラブルや診療拒否事例が報告されています。
スペインで高熱を出した女性が病院を訪れたところ、現地語が通じず、保険もないことから治療を断られてしまい、そのままホテルに戻るしかなかったという体験談があります。
数日後に帰国できたものの、日本で診断された結果は肺炎でした。
「診てもらえない」「説明できない」そういった不安から逃れるためにも、保険とサポートデスクの存在は欠かせません。
SNSで「入っておけば…」と後悔の声多数
SNSや口コミサイトでは、「海外旅行保険に入っておけばよかった」という声が日々投稿されています。
多くは金銭的な負担だけでなく、心の余裕を失ったことへの後悔に満ちています。
Twitterやnoteには、「軽い腹痛だと思っていたのに手術に…」「スマホ盗まれて大損害」「予約変更もできず泣く泣く帰国」など、さまざまな“備え不足”の失敗談が投稿されています。
バリ島でひったくりに遭った方が「保険に入ってなかった自分を責めた」という投稿をしており、それがバズったことで「私も同じ経験あります」と共感の声が多数寄せられました。
旅行保険は“使うかどうか”ではなく、“使う必要が出たときにあるかどうか”が重要です。SNSで後悔の声を見かけたら、それを自分ごととして捉えることが、正しい判断につながります。
海外旅行保険の選び方と賢い節約術
これから、自分に合った海外旅行保険を選ぶ方法と、無理なく節約しながらしっかり備えるコツについて解説します。
- 5-1. 自分に合う保険の選び方(旅行先・日数・目的別)
- 5-2. ネットで安く・簡単に入れるおすすめサービス
それでは一つずつ解説します。
自分に合う保険の選び方(旅行先・日数・目的別)
滞在日数と行き先で必要な補償は変わる
旅行の内容によって、必要な補償の「量と質」は変わってきます。
特に重要なのが「滞在日数」と「行き先の医療事情」。
医療費が高額な国では高い補償額が必要になりますし、長期滞在なら入院リスクにも備える必要があります。
ジェイアイ傷害火災保険のデータによれば、1週間以内の短期旅行と1ヶ月を超える長期滞在では、保険金の平均請求額が約3倍違うという結果も出ています。
アメリカへ10日間旅行した人は、盲腸の緊急手術と入院で約280万円の医療費がかかりましたが、短期旅行者向けの保険では補償額が足りず、差額を自己負担する結果に。
逆に、東南アジア5日間の旅行では、補償額を抑えても十分カバーできていました。
一律の保険ではなく、「その旅に必要な補償かどうか」で選ぶことが、安心と節約のバランスを取るポイントです。
個人旅行・団体旅行・留学で選ぶべき補償とは
旅行の「スタイル」や「目的」によって、重視すべき補償内容も変わります。
ひとり旅ではトラブル対応がすべて自己責任になるため、通訳サポートや緊急連絡体制のある保険が重要です。
団体旅行では手荷物トラブルや遅延、留学なら長期の医療補償や賠償責任への備えが欠かせません。
学生総合共済の調査では、留学中の保険請求のトップ3は「通院」「携行品損害」「第三者への賠償」とされており、一般的な旅行保険では対応しきれないケースも多くあります。
ヨーロッパでの短期語学留学中に寮の部屋の水道を壊してしまった高校生が、数十万円の修理費を求められたという事例では、留学生向け保険の賠償責任補償で全額カバーされました。
旅の種類によって想定すべきリスクは異なります。「何が起こるか」ではなく「どんな旅か」に合わせて、保険を選ぶ視点が大切です。
家族旅行なら「ファミリープラン」がお得
家族で旅行する場合、個別に保険に加入するよりも、家族全員をまとめて補償する「ファミリープラン」を選ぶことで保険料が抑えられるケースがあります。
補償内容が一括で管理できる点もメリットです。
AIU保険や東京海上日動のファミリープランでは、大人2名+子ども2名で1人ずつ加入するよりも15〜20%安くなるプランも用意されています。
グアムに家族4人で旅行したご家庭では、個別加入では約1万6,000円かかるところ、ファミリープランなら1万2,000円で同等の補償が受けられました。
さらに、家族の誰かがトラブルに遭った場合でも、他のメンバーが一緒にサポートを受けられるという安心感も得られます。
「家族旅行だからこそ」保険料もリスクもスマートにまとめられる。
そう考えると、ファミリープランは費用対効果の高い選択肢です。
ネットで安く・簡単に入れるおすすめサービス
比較サイトで一括見積もりできるサービス
旅行保険は数多くの商品があるため、選び方に迷ってしまうことも。
一括見積もりサイトを使えば、自分の条件に合った保険を複数社から比較でき、料金・補償内容・口コミなどもまとめて確認できます。
「保険市場」「価格.com保険」「i保険」などの比較サイトでは、最短3分で見積もり結果が表示され、そのままオンライン契約まで完了できる仕組みになっています。
実際、初めての海外旅行に行く大学生が保険市場を使って見積もりを比較したところ、同じ補償内容でも2,000円以上の差があることに気づき、費用を抑えながら安心できる保険に加入できたといいます。
自分で調べるのが不安な人こそ、比較サイトを使って「見える化」された情報で安心を得ることができます。
1日数百円で入れるネット完結型の保険
保険は「高い」「手続きが面倒」というイメージがありますが、最近では1日数百円から加入でき、申し込みも5分以内で終わるネット専用保険が増えています。
スマホひとつで完結するため、出発前日でも気軽に加入できるのが魅力です。
ソニー損保やジェイアイ傷害火災の「t@biho(たびほ)」では、1日あたり400〜600円程度で補償内容をカスタマイズできるプランが人気。通院・入院・携行品補償などを自由に組み合わせられるのが特徴です。
沖縄旅行前日に突然の天候不安で不安になった夫婦が、t@bihoで前夜にネット加入し、旅行中に子どもがケガをした際もキャッシュレス診療を受けることができたという声もありました。
気軽に、でもしっかり守れる。それが今どきのネット保険のスタンダードです。
保険会社選びで見るべき3つのポイント
どの会社の保険にするかを決めるとき、注目したいのは以下の3つの視点です
- 【補償範囲】医療・携行品・救援・賠償などが網羅されているか
- 【サポート体制】24時間日本語対応があるかどうか
- 【支払いのしやすさ】キャッシュレス診療対応や迅速な保険金支払い
とくに初めての海外旅行や家族連れの場合、「サポートの質」はとても大切です。
通訳対応や現地病院との連携が弱い会社を選んでしまうと、せっかく保険に入っていても使いこなせないリスクがあります。
バリ島で感染症にかかった旅行者は、サポートセンターの対応が迅速だったおかげで、日本語通訳つきの病院で適切な診療を受けられたと語っています。
保険は価格だけでなく、「万一のときに頼れるか」で選ぶ。そうすることで、本当の意味で“損しない”保険選びができます。
海外旅行の時に保険って必要のまとめ
海外旅行保険は、予期せぬ医療費やトラブルから身を守る大切な備えです。
クレジットカード付帯保険では補償が不十分な場合も多く、目的や滞在日数に応じた保険選びが欠かせません。家族旅行や留学、個人旅行など、スタイルに合ったプランを選ぶことで、安心もコストパフォーマンスも得られます。
ネットで手軽に加入できるサービスを活用しながら、必要な補償を見極めましょう。
- 海外の医療費は高額。保険がないと数百万円の請求も
- クレカ付帯保険は「利用条件」「補償額」に要注意
- キャッシュレス診療や日本語サポート付き保険が安心
- 家族旅行には「ファミリープラン」が経済的
- 比較サイトやネット完結型保険でお得に加入可能
海外旅行の時に保険は必要のよくある質問
Q1. クレジットカードに海外旅行保険が付いていれば十分ですか?
A.付帯しているだけでは安心とは言えません。まず「自動付帯」か「利用付帯」かの違いを確認しましょう。利用付帯なら旅費の支払いにそのカードを使わないと保険は適用されません。また、補償額が100〜200万円と低めで、医療費が高い国では全く足りないケースも。目的地や滞在日数に応じて、別途保険を検討するのが賢明です。
Q2. キャッシュレス診療ってどういうものですか? どの保険でも使えますか?
A.キャッシュレス診療とは、現地の提携病院で診療を受ける際、その場で現金を支払わずに済む仕組みです。保険会社が病院へ直接支払うので、本人はパスポートと保険証を見せるだけでOK。すべての保険が対応しているわけではなく、提携病院の有無やエリアも重要なので、事前に確認しておきましょう。
Q3. どの保険会社を選べばいいのか迷います。比較するポイントはありますか?
A.まずは「補償範囲(医療・携行品・賠償など)」「24時間日本語サポートの有無」「キャッシュレス診療に対応しているか」の3つをチェックしましょう。比較サイトを使えば、一括見積もりでプランを比較でき、無駄なく選べます。価格だけでなく、トラブル時に「ちゃんと使えるか」も重視して選ぶのがコツです。