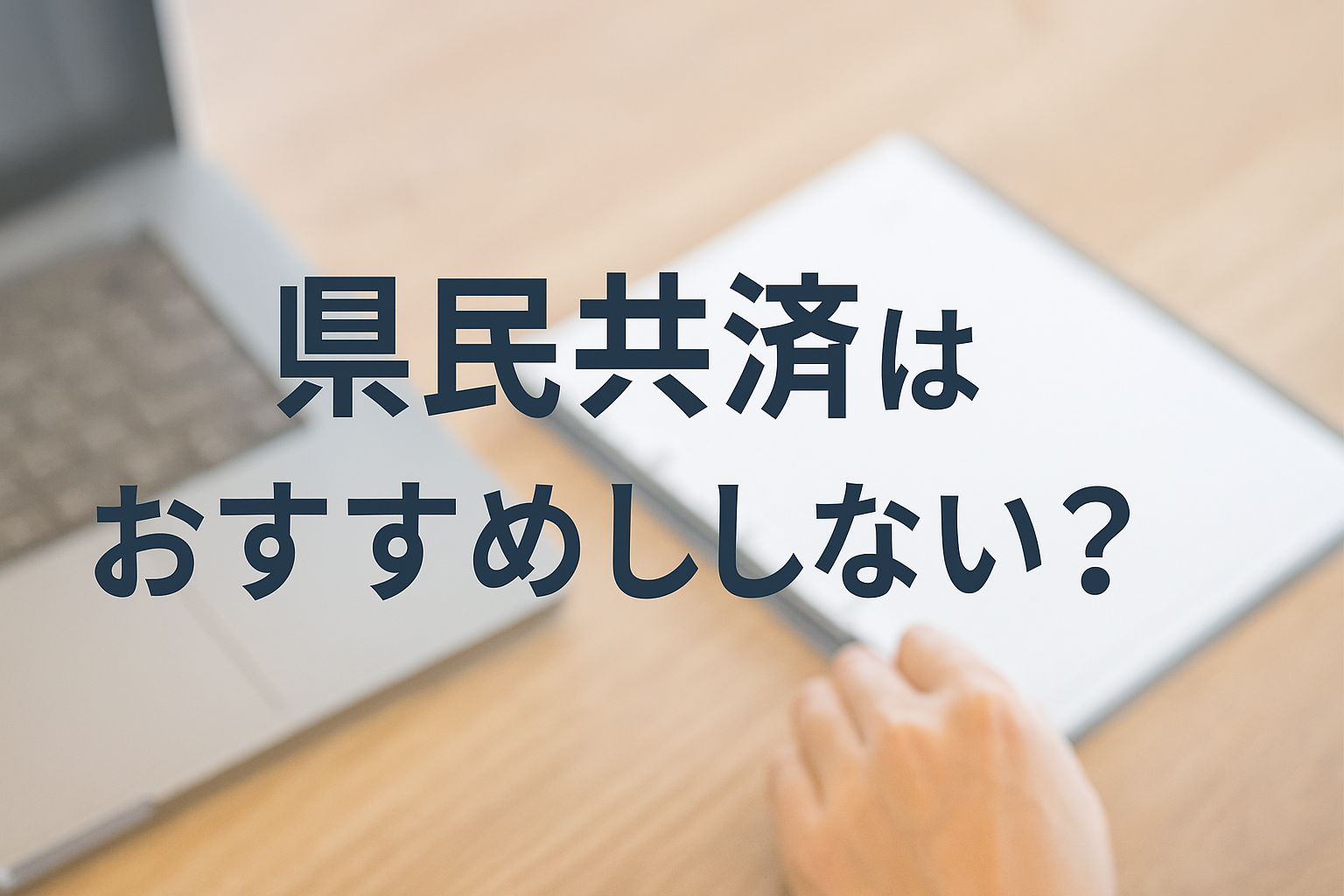保険料が安くて手軽に加入できる県民共済。
でも「安い=安心」ではないかもしれません。
実際に加入してから「思ったより保障が少ない」「手続きが煩雑だった」と後悔する人も。
この記事では、県民共済が向いている人・向かない人の違いや、よくある誤解、注意点をわかりやすく解説します。
あなたにとって本当に必要な保障とは何か、一緒に考えてみませんか?
- 県民共済は掛け金が安くシンプルな保障が魅力。
- ただし、保障内容の薄さから後悔する人も少なくありません。
- 自分に合うかを見極めるための判断ポイントと注意点を詳しく解説します。

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
そもそも「県民共済」はどんな保険?
これから「県民共済」の仕組みや特徴について解説します。
共済と民間保険の違いとは
保険と共済の基本的な仕組みの違い
保険と共済の大きな違いは、「営利か非営利か」という運営スタンスにあります。
県民共済は、営利を目的としない非営利団体が運営しており、集めた掛金は主に加入者への給付と必要最低限の運営に使われます。
対して、民間保険会社は株式会社として利益を出すことが目的の一つであり、掛金の一部が会社の利益として計上されます。
そのため、県民共済の掛金は一般的に安く設定されており、保障も必要最低限に絞られています。一方で、民間保険は特約の種類が豊富でオーダーメイドのような保障を組める一方、月額費用が割高になりやすい傾向があります。
民間の医療保険で月額5,000円〜10,000円かかるところを、県民共済なら月額2,000円前後でカバーできると感じて加入する人も多いようです。
共済はあくまで「みんなで助け合う」考え方に基づいた仕組みであり、民間保険のような手厚さはないものの、コスパ重視の人には選ばれやすい仕組みになっています。
加入条件・審査・保障の考え方の違い
県民共済と民間保険では、加入時の審査や保障の前提にも違いがあります。
県民共済は、基本的に地域に住んでいれば誰でも入れる開かれた仕組みで、医療共済においては持病があっても加入できるケースも少なくありません。加入時の健康告知も、民間保険ほど厳密ではなく、あくまで「相互扶助」の立場で柔軟に受け入れられているのが特徴です。
それに対して、民間保険は健康状態や既往歴に対して厳密な審査を行います。入院歴や服薬状況によっては加入を断られることもありますし、場合によっては条件付き加入や保険料の割増が発生することもあります。
病気が心配な人や過去に治療歴がある人にとっては、県民共済のゆるやかな加入条件が大きな安心材料になるかもしれません。
県民共済の基本的な保障内容と仕組み
医療保障の内容と限度額
県民共済の医療保障は「シンプルでわかりやすい反面、限度がある」とよく言われます。たとえば入院給付金は1日5,000円が基本で、手術給付も定額です。先進医療や通院補償など、最近の医療保険に多い保障は基本的にカバーされません。
とはいえ、ちょっとした入院や軽度の手術であれば、最低限の備えにはなります。月額2,000円で入院給付金が出る仕組みは、負担感の少なさという意味では魅力的です。
実際に「大きな病気ではなかったから県民共済で十分だった」という声もあり、健康な間の“万一への備え”として割り切って使っている人も少なくありません。
ただし、長期入院や高額医療を想定すると、民間の医療保険と比べて心許ないのも事実です。
1-2-2 死亡保障の仕組みと給付金の金額
県民共済の死亡保障は、年齢に応じて給付金が変動する仕組みになっています。たとえば30代では最大400万円ほどの死亡保障がついているのに対し、60歳を超えると給付額が大幅に下がる傾向があります。
保障内容は「定額制」で分かりやすい反面、家族の生活を支える目的としては不十分に感じる人もいるかもしれません。特に子育て中の家庭や住宅ローンを抱えている世帯にとっては、万一のときに足りないと感じる可能性もあります。
「必要最低限を割安で」というスタンスであれば問題ないのですが、「遺された家族の暮らしを守る」観点では、民間の収入保障保険や終身保険などと比較検討する必要があるでしょう。
なぜ人気?県民共済の加入者が多い理由
月額掛金の安さとシンプルな仕組み
県民共済が多くの人に選ばれる理由のひとつが、毎月の掛金が非常に安いことです。
医療型でも月額2,000円前後と、家計への負担が少ない点が評価されています。
保障内容も“パッケージ型”になっており、複雑な選択肢が少ないぶん、保険に詳しくない人でも入りやすいのが魅力です。
「保障が足りるか不安はあるけど、保険って難しくて選べないし、ひとまず県民共済で」という人も多く、加入のハードルが低いことが、加入者数の多さにもつながっています。
掛け捨てだけど一部戻る「割戻金制度」
県民共済には、年に一度「割戻金」が支払われる仕組みがあります。
これは、1年間に集まった掛金の余剰があれば、それを加入者に分配するという仕組みです。
たとえば、ある年に大きな給付が少なければ、その分多くの割戻金が戻るというわけです。
これにより「掛け捨て」の保険ではあるものの、完全にゼロにはならないという安心感が生まれます。
過去の実績では、年間の掛金の20〜30%が戻ることもあり、実質の負担がさらに軽くなるといったメリットがあります。
この“お金が戻ってくる”という感覚が、県民共済の「お得感」をさらに高めていると言えるでしょう。
「おすすめしない」と言われる理由
これから「県民共済が人によってはおすすめできない」とされる理由について解説します。
保障内容がシンプルすぎる?実際の補償範囲
入院日額5,000円では足りない?
県民共済の医療保障は、入院1日あたり5,000円が基本です。短期間の入院や軽い病気なら十分かもしれませんが、手術や長期入院になると心もとないと感じる人もいます。
厚生労働省のデータによると、入院1日あたりの平均費用は約2万1,000円(2021年「医療費の動向」)とされており、5,000円では自己負担分を十分にカバーしきれないケースが多いことがわかります。
たとえば、整形外科の手術で10日入院した人の話では、医療費や食事代、個室料などを合わせて15万円以上かかり、県民共済から支払われた給付金では半分にも届かなかったそうです。
最低限の備えとしては役立つ一方で、実際の医療費に対しては不十分な場面も多く、過信しすぎるのは避けた方が良い保障内容です。
通院や先進医療には非対応な点も多い
県民共済の大きな特徴として、通院補償や先進医療のカバーがないことが挙げられます。
入院や死亡に関する保障はあるものの、がん治療などで多用される通院治療や放射線治療などには給付が発生しないケースもあります。
特に最近は、入院を伴わずに治療が完結するケースも増えてきており、「通院が多くて入院していないから給付が出なかった」という不満も見受けられます。
知人は乳がん治療で複数回の通院を行いましたが、県民共済からは1円も給付が出ず、結局は医療費をすべて自己負担したそうです。
現代の医療事情にマッチしていない点が、県民共済のデメリットとして認識されることにつながっています。
入院・手術の保障が物足りないという声
2-2-1 他社の医療保険との保障額比較
県民共済の入院・手術給付金は、他社と比べると明らかにシンプルかつ低額に設定されています。
入院は1日5,000円、手術給付金も1〜10万円が中心で、複雑な条件やランク分けがない反面、十分とは言えない場面も多くあります。
民間保険では、入院1日1万円・手術給付20万円・通院保障付きなどのプランが主流になってきており、充実度には大きな差があります。
しかも特約を追加することで、がんや先進医療にも対応できる柔軟性が高いのが特徴です。
がんの手術で7日間の入院をしたある40代男性は、県民共済から35,000円の入院給付+数万円の手術給付を受けたそうですが、全体の医療費には全く足りなかったと感じたと話しています。
掛金の安さは魅力ですが、保障の厚さを重視したい人には物足りなさが残る構成です。
長期入院や高額医療に弱い理由
県民共済の保障は、長期入院や高額な治療が続くケースにはやや対応しにくい設計になっています。
支給日数の上限が短めで、60日や124日が上限となっているプランも多く、慢性疾患などで長期治療が必要な場合にはリスクがあります。
また、1入院あたりの支払上限額もあるため、高額療養費制度を使っても全額はカバーしきれないことが想定されます。加えて、病状によっては途中で保障対象外になることも。
難病指定を受けて入退院を繰り返している知人は、県民共済の保障では十分ではなく、結果的に民間の医療保険に入り直したとのことでした。
短期間のリスクには強くても、長期にわたるリスクには脆さが残る設計になっている点には注意が必要です。
年齢が上がると保障が減る仕組みとは?
60歳以降の保障内容の変更
県民共済では、一定年齢を過ぎると保障内容が縮小される仕組みが採用されています。
たとえば、60歳以降になると死亡保障が半額になるなど、給付額が大きく減額されます。
保障が減っていく理由は、非営利団体として公平性を保ちつつ、掛金を一定に保つためのコストバランスによるものです。
しかし、加入者側としては「老後こそ必要なのに減らされるの?」という不安を感じやすくなります。
70歳の父が加入していた県民共済では、病気死亡時の保障額が80万円まで減額されていて、家族としては少し驚きました。
年齢を重ねたあとも手厚く保障される設計ではない点を踏まえた上で、選ぶ必要があります。
高齢化に伴う必要保障とのギャップ
高齢になると医療費や介護費用がかさみますが、県民共済の保障はそれに比例して増えるわけではありません。
むしろ、逆に保障が縮小される構造のため、必要保障額とのギャップが生まれやすくなっています。
総務省の調査によると、高齢世帯の医療費自己負担は平均で年間約20万円を超えています(家計調査より)。
これに対し、県民共済の給付が1回の入院につき3万円〜5万円程度では、決して十分とは言えない状況になります。
高齢の母が入院した際にも、共済からの給付は限られており、差額ベッド代や食事代などはすべて自己負担でした。
老後の安心を保険で支えるという目的には、あまり向いていない仕組みだと言えそうです。
生命保険としての「弱さ」
万一のときの保障額の少なさ
県民共済の死亡保障は、年齢や原因(病気・事故)によって異なりますが、最大でも数百万円に留まります。
特に病気死亡は400万円前後が上限で、年齢が上がるにつれて減額されていきます。
一般的な民間生命保険では、必要保障額として1,000万円〜2,000万円を目安とするプランも多く、万一の際の生活保障としては格差が大きくなります。
30代の夫が亡くなった家庭では、県民共済から300万円の給付がありましたが、教育費や住宅ローンには到底足りず、結局、別の民間保険に頼らざるを得なかったそうです。
単体で十分な生命保障を期待するには、心許ない設計になっていることは否めません。
遺族の生活を支えるには不十分?
遺された家族が生活を継続していくためには、継続的な収入の代わりとなる保障が必要です。
しかし、県民共済の保障は一時金のみであり、収入保障型のように定期的に給付される仕組みは用意されていません。
民間の収入保障保険では、亡くなった後に月々10万円ずつ支給されるといった形もあり、教育費や生活費の見通しが立てやすくなります。
遺族年金だけでは足りず、民間保険の月払い給付があって助かったという話は多く、県民共済だけに頼るリスクは大きいと感じます。
生活を支える目的ならば、他の保険との組み合わせを前提に考えた方が安心です。
実際に加入して後悔した人の声と理由
これから、実際に県民共済に加入した方の口コミや体験談をもとに、後悔につながった具体的なケースや注意点について解説します。
口コミから読み解く「後悔」のパターン
想定外の入院費用を補えなかった
「最低限の備えにはなるけど、実際は足りなかった」という声は少なくありません。
県民共済の入院給付は1日5,000円が一般的ですが、医療費の自己負担はそれだけでは済まないこともあります。
差額ベッド代や入院中の食事代、日用品など、実費負担がかさむのが現実です。
厚生労働省の「医療費の状況」によれば、1日あたりの入院費の自己負担は平均で2万円程度に上るケースもあります。
すると、共済の給付だけでは半分にも届かないということになります。
胃の内視鏡手術で1週間入院した方は、実費で12万円以上の請求があり、共済からの給付は3万5千円ほど。
「あくまで“補助的”なものであって、安心できる額ではなかった」と感じたそうです。
共済の安さには魅力がありますが、費用がかかる場面では「足りない」と痛感する方が多いようです。
給付金の申請手続きがわかりにくい
給付金を受け取るための手続きが想像以上に煩雑で、戸惑ったという意見もあります。
医師の診断書や領収書、加入者番号の記載など、提出すべき書類が多く、初めての人にとってはハードルが高く感じることも。
特に高齢の加入者や家族が手続きを代行する場合には、記入ミスや書類不足で差し戻しになったという体験談も目立ちます。
父が入院した際に申請を行いましたが、必要書類の案内が曖昧で、3回も書類を出し直す羽目になりました。
その結果、給付金の振込までに1か月以上かかり、支払いを先に済ませていた家計に響いたのを覚えています。
給付される内容よりも「申請の手間」で疲弊することもあり、サポート体制の薄さに後悔する方もいます。
加入前に気づかなかった落とし穴
加入年齢によっては不利になる場合も
県民共済は基本的に全年齢で掛金が一定ですが、そのぶん年齢が上がると保障内容が少しずつ減額される仕組みになっています。
特に60歳を超えると、死亡保障や入院保障の金額が一気に下がる傾向があります。
これを知らずに「一生安心」と思い込んで加入した人が、後から内容の変化に驚くケースが多いようです。
55歳で加入したある男性は、65歳時点で保障が半分になったことに気づかず、いざ病気になったときに「こんなに少ないの?」とショックを受けたそうです。
若い頃は安心でも、年を重ねるほどに「想定していた保障と違う」と気づく落とし穴があることを覚えておく必要があります。
保障の更新時の見落としがちな注意点
県民共済は1年ごとに自動更新される仕組みですが、その際に保障内容が変わる場合があります。
見落とされがちなのが、「通知があっても確認しないまま継続してしまう」ケースです。
保障内容が変更になっていたことに気づかず、事故や病気の際に「思っていた保障が受けられなかった」という声は少なくありません。
知人の女性は、60歳を過ぎたタイミングで保障が変更されたことに気づかず、医療費の補償が減っていたため、申請時に支給額が期待よりも低くて困惑していました。
自動更新に安心しすぎず、毎年の「保障内容通知書」や「変更案内」をきちんと読むことがとても大切です。
解約を決めた理由ランキング
他社の医療保険に乗り換える人が多い理由
県民共済を解約する理由で多いのが、「保障内容の薄さに不安を感じた」というものです。
特に、家族構成の変化や持病のリスクが高まる40代以降になると、「もっと手厚い保険が必要」と考える人が増えてきます。
民間保険への乗り換えを検討する理由としては、以下のようなものが挙げられます:
- 通院・先進医療への保障が充実している
- 長期入院や収入補償もカバーできる
- サポート体制が充実していて申請がスムーズ
子どもが生まれたタイミングで、県民共済をやめて民間の医療保険に切り替えたという友人は、「万一に備えるなら、もう少し手厚さがほしい」と話していました。
掛金の安さよりも、「いざというとき本当に安心できるか」を重視した結果の選択が、乗り換えの理由になっているようです。
ライフステージの変化と保険の見直しタイミング
結婚や出産、転職や老後といったライフステージの変化にあわせて、保険を見直す人は多くいます。県民共済は「独身時代の最低限の保障」としては有効でも、家族ができたり、将来の医療リスクが増してきたりすると、保障の物足りなさが気になってきます。
特に40代以降は、健康診断の結果に不安を覚えたり、知人の病気をきっかけに「この保障で大丈夫?」と考え直す人が増えます。
保険は一度入ったら終わりではなく、ライフステージごとに柔軟に見直すべきものであり、必要に応じて県民共済からの卒業を考えるのも自然な流れです。
県民共済が合わない人・向いている人
これから、県民共済が向いている人とそうでない人の特徴を、それぞれのライフスタイルやニーズ別にわかりやすく解説していきます。
最低限の保障でいい人には合う?
健康体で通院・入院の心配が少ない人
普段から健康管理をしっかりしていて、病院にかかることもほとんどない。
そんな人にとっては、県民共済の「最低限の医療保障」はちょうどいい選択肢になります。
必要以上の保障にお金をかけたくない人にとって、月々1,000円〜2,000円という掛金は非常に手頃です。
若年層の健康な男女は、国民健康・栄養調査でも「医療機関の受診回数が年に数回程度」というデータが出ており、医療費自体が少ない傾向にあります。
20代の知人は、「今のところ病院に行くことなんて年に1〜2回。
とりあえず何かあったときのために、最低限の保障があればいいかなと思って共済を選んだ」と話していました。
健康リスクが低い時期には、シンプルな共済のスタイルはコストパフォーマンスの面でも納得できる選択肢です。
年齢が若く貯蓄がある独身層
独身で生活に余裕があり、ある程度の貯蓄も確保できている人には、県民共済の「割り切った保障」は向いています。もしものときは貯金でまかなう前提で、保険に大きなお金をかける必要はないと考える層です。
実際、金融広報中央委員会の調査では、20代・30代の約4割が「貯蓄で医療費をカバーできる」と回答しています。
一人暮らしをしている30代女性は、「貯金もあるし、健康だから通院・入院の不安は今のところ少ない。
県民共済ならコストが抑えられて気持ち的にもラク」と話していました。
保険でがっちり固めるよりも、貯蓄+簡易的な保険という考え方をする人には、県民共済の仕組みがフィットしやすいです。
子育て世代や高齢者にはどう?
子ども向け保障のメリットと限界
県民共済には「子ども型」のプランがあり、月1,000円程度で入院や死亡保障をカバーできます。軽いケガや発熱などで医療機関にかかる機会の多い未就学児にとっては、コスパのよい選択肢といえます。
文部科学省のデータでは、6歳未満の子どもは年間20回以上医療機関を受診している傾向にあり、医療費は高くなる一方で、乳幼児医療助成などで自己負担は少ないのが一般的です。
保育園に通う子を持つママは、「共済でちょこちょこ給付が出るのはありがたい。
でも、大きな病気のときはちょっと不安かも」と語っていました。
小さなリスクに対しては強いけれど、大病や手術といったケースでは物足りなさが出るため、子どもの保障としては目的を明確にしたうえで選ぶ必要があります。
高齢者にとっての注意点と必要保障とのズレ
年齢が上がるにつれて、県民共済の保障内容は徐々に減額されていきます。
特に60歳を過ぎると死亡保障額が半分近くに下がるなど、老後の安心とは少し方向性が異なる設計です。
高齢者の医療費自己負担は、総務省の家計調査によれば年間20万円以上に達することも珍しくありません。
70代の母が入院したときは、入院費用はもちろん、差額ベッド代・食事代なども含めて高額になりましたが、共済からの給付額はそのうちのごく一部。
結果的に、民間保険の方が良かったのではと考えさせられました。
高齢者にとっては、割戻金や安い掛金よりも「どれだけしっかり備えられるか」が重要になります。
共済だけで備えるには少し不安が残ります。
医療費がかさむ職種・生活スタイルとの相性
自営業・フリーランスと県民共済の相性
自営業やフリーランスの方は、病気やケガによって働けなくなると収入に直結します。
そんな職種にとって、最低限の医療保障しかない県民共済では「足りない」と感じるケースが多くなります。
収入保障型の保険などをセットで備えるならともかく、共済単体では「仕事を休んだときの補償」がないため、経済的リスクが大きくなりがちです。
イラストレーターとして活動する知人は、ぎっくり腰で1週間寝込んだときに「共済では医療費は出たけど、仕事が止まったぶんのカバーがなかった」と感じたそうです。
収入が不安定な立場の人こそ、より幅広い保障がある保険との併用が求められます。
医療費が高額になりやすい職業の人にとってのリスク
介護職、建設業、夜勤を含む業種など、身体に負担がかかる職業では、病気やケガのリスクも高まりがちです。県民共済のように「入院1日5,000円」「手術は数万円程度」といった設計では、実際の出費をカバーしきれない場面も増えてきます。
厚労省の労災統計でも、肉体労働や夜勤職の疾病リスクは他業種に比べて高い傾向にあるとされています。
現場作業員の男性は、夏場の熱中症で入院した際、点滴・検査などを含めて10万円以上かかり、「共済からは3万円くらいしか出なかった。結局、貯金を崩すことになった」と語っていました。
身体を使う仕事の人こそ、想定外の医療費に備えるためには、より手厚い保障の必要性が高まります。
県民共済が合わない人・向いている人
これから、「県民共済がどんな人に向いているのか、または向かないのか」について解説していきます。
- 健康体や独身層など、最低限の保障で満足できる人には適しているのか
- 子育て世代や高齢者にとっての向き不向き
- 自営業や医療費が高くなりやすい職業との相性
それでは一つずつ解説します。
最低限の保障でいい人には合う?
健康体で通院・入院の心配が少ない人
健康で普段から医療機関にかかる機会が少ない人には、県民共済のシンプルな保障内容が合っています。
病気やケガのリスクが低ければ、高額な民間保険に加入する必要性があまりなく、共済で十分という考え方も自然です。
厚労省の統計によると、20代〜30代の通院頻度は年間数回程度とされており、医療費の負担自体が少ない傾向にあります。
IT系企業に勤める30代男性は「会社の健康診断でも毎年異常なし。
共済は無駄なく最小限の保険として使えてちょうどいい」と話していました。
ムダなく、最低限の備えをしたい人にとっては、県民共済はコストパフォーマンスの高い選択です。
4-1-2 年齢が若く貯蓄がある独身層
独身で経済的にも余裕があり、ある程度の貯蓄がある人は、医療保険に過剰な備えを求める必要がないこともあります。県民共済の掛金の安さは、そういった人たちにとって大きなメリットです。
金融広報中央委員会の調査では、30代以下の約4割が「医療費は貯金で対応できる」と考えています。
20代女性のケースでは、「月2,000円以内で入れるし、貯金があるからあまり心配していない。保険料を浮かせて旅行や自己投資に回している」と話してくれました。
貯金で医療費をまかなえる前提がある若年層にとっては、県民共済のような掛け捨ての共済保険は、身軽で合理的な選択になり得ます。
子育て世代や高齢者にはどう?
子ども向け保障のメリットと限界
子ども向けの共済プランは、保険料が安く、ちょっとした入院やケガでも給付金がもらえる点が魅力です。
乳幼児医療費助成と合わせて使えば、家庭の医療負担をさらに抑えることができます。
子どもの医療機関受診回数は非常に多く、文部科学省の調査では年間20回を超えることもあります。
3歳のお子さんを持つ家庭では、「風邪で入院したとき、共済から給付が出て本当に助かった。
ただ、大きな病気や手術となるとちょっと不安かな」と感じたそうです。
軽微なトラブルには強い反面、重症時の保障や長期的な医療ケアには限界がある点を理解しておく必要があります。
高齢者にとっての注意点と必要保障とのズレ
県民共済は年齢とともに保障額が段階的に減っていくため、高齢者にとっては必要な医療費に対して給付が追いつかない可能性があります。
特に死亡保障や入院保障が60歳以降から大幅に下がる点は見落とされがちです。
総務省の調査では、70代以上の1人あたり年間医療費は20万円を超えるとされています。
65歳の父親が入院した際、「保障が昔より減っていたことを知らず、思ったほど給付されなかった」と戸惑っていました。
安心した老後を考えるなら、年齢に応じて必要な保障額を見直し、県民共済だけに頼らない設計が必要になります。
医療費がかさむ職種・生活スタイルとの相性
自営業・フリーランスと県民共済の相性
自営業やフリーランスは、病気やケガで仕事を休むと直接的に収入に影響します。
しかし、県民共済には「収入保障」がないため、長期の療養には弱いというデメリットがあります。
2022年の中小企業庁の調査でも、個人事業主の約6割が「収入減少時の備えに不安がある」と回答しています。
フリーランスで活動しているカメラマンの男性は、肩の腱板損傷で1か月仕事ができず、「医療費は出たけど、生活費は自腹。保障の薄さを痛感した」と話していました。
保障が「入院や手術の費用」に限られる共済では、自営業のような収入変動の大きい人には不十分な可能性があります。
医療費が高額になりやすい職業の人にとってのリスク
夜勤や肉体労働、リスクの高い業務に就く人は、どうしても医療費がかさみやすくなります。
県民共済の一律の保障額では、実際の医療負担に対応しきれない場面が出てきます。
厚労省の労働安全衛生調査では、建設業・運送業・介護職などの労働災害や疾病リスクは、他業種に比べて高い傾向があります。
夜勤シフトが多い看護師の女性は、「体調を崩して入院したとき、県民共済の給付だけじゃ全然足りなかった。
医療保険に入り直そうかと思ってる」と話してくれました。
医療リスクの高い仕事に就く人ほど、保障の手厚さが求められます。
県民共済は最低限の備えとしては有効ですが、カバーしきれない部分が多いのも事実です。
県民共済をおすすめしない人の特徴とは
これから、「県民共済が合わないと感じる人の共通点や、後悔しないために確認すべき視点」について解説していきます。
- 自分の生活環境と保障内容のズレ
- 掛け金の安さにひかれて失敗するケース
- 比較すべき項目や、ライフステージごとの見直しの重要性
それでは一つずつ解説します。
見落としがちな注意点と判断基準
自分の生活環境に本当に合っているか見極める
保障内容がどれだけシンプルでも、自分のライフスタイルに合っていなければ意味がありません。
病気リスクが高い職業や家族構成、将来の出産予定などを踏まえて、自分にとって本当に必要な保障を明確にすることが大切です。
厚生労働省の「国民生活基礎調査」でも、世帯構成や職業によって医療費・通院率・入院率は大きく異なることが報告されています。
独身時代には県民共済で十分だと感じていた人が、結婚・出産後に医療費や保障への不安が大きくなり、民間保険に切り替えたという声もよく耳にします。
選ぶ前に「自分が将来どう生きたいか」という視点を持つことが、後悔のない選択につながります。
掛け金の安さだけで選ぶリスク
「月1,000円〜2,000円で加入できる」という価格だけに注目して選ぶと、肝心なときに「保障が足りなかった」という事態になりかねません。保障が薄くても、割戻金があっても、支えきれない現実があることを見落としてはいけません。
金融庁の資料でも、「保険を価格だけで選んだ人の後悔率は高い」という調査結果が出ています。
30代男性は「安さだけで県民共済を選んだけど、手術と長期入院で給付が少なく、結果的に貯金を大きく崩すことに。
あのときしっかり見直しておけばよかった」と後悔を話していました。
“安さ”は魅力ですが、“安心”とはイコールではないことを意識して判断することが大切です。
後悔しないために比較すべきポイント
保障内容の“質”をチェックするポイント
見落としがちですが、「どんなときに、いくらもらえるのか?」という具体的な給付条件を細かく比較することが重要です。入院日額、手術給付、先進医療対応などをチェックし、生活費や収入の補償があるかも確認しましょう。
各社の医療保険比較では、入院1日あたり1万円以上・手術10万円以上を保障するプランが一般的となっています。
ある40代女性は、「県民共済は1日5,000円しか出なかったから、個室を選んだ分の差額ベッド代に全く足りなかった」と振り返っていました。
数字だけではなく、「どんなときに困るのか」をシミュレーションしてみることで、本当に必要な保障の“質”が見えてきます。
ライフステージごとの必要保障額の見積もり方
独身・結婚・出産・老後と、人生の段階によって必要な保障は大きく変わります。
自分の今とこれからを見据えたうえで、どのタイミングで見直し・乗り換えが必要かを把握しておくことが、後悔しない保険選びのカギです。
日本FP協会のガイドラインでも、30代以降は「万一のときに家族を支える保障額」が重視されるとされています。
子どもが生まれてから保険を見直した30代パパは、「今までは県民共済で十分だったけど、遺族保障を考えると足りないことが分かって見直した」と話してくれました。
“今だけ”ではなく、“未来も含めた視点”で保険を捉えることが、後悔を防ぐ大きなポイントです。
県民共済をおすすめしないは本当のまとめ
県民共済は「安さ」と「シンプルさ」が魅力ですが、すべての人に向いているわけではありません。
特に医療費がかさみやすい家庭や、将来の保障を重視したい人には不向きな面もあります。
保障の質や将来のライフステージを見据え、後悔しない保険選びをすることが大切です。
- 掛け金が安くても保障内容はシンプルで最低限
- 年齢が上がると保障額が減少する仕組みに注意
- 自営業や高リスク職種には保障が不十分な場合も
- 子育てや高齢期には手厚い保障が求められる
- 「今」と「これから」に合うかを見極める視点が必要
県民共済はおすすめしないのよくある質問
Q1. なぜ県民共済は「おすすめしない」と言われることがあるのですか?
A. 県民共済は掛け金が安くて加入しやすい反面、保障内容がシンプルで最低限にとどまるためです。
入院1日5,000円や手術給付の限度が低く、高額医療や長期入院には対応しきれない場面もあります。
ライフステージや職業によっては、保障が不十分だと感じる人も多くいます。
Q2. 県民共済に加入して後悔するのはどんなケースが多いですか?
A. 「いざというときに思ったほど保障されなかった」という声がよく見られます。
特に医療費がかさんだときや、家族ができて必要な保障が増えたときに、「保障が足りない」と実感する人が多いです。掛け金の安さに惹かれて深く考えずに加入してしまった結果、後悔につながるケースがあります。
Q3. 県民共済はどんな人に向いていますか?
A. 医療リスクが低く、最低限の保障で十分と感じている人には向いています。
たとえば、健康体の独身者や貯蓄に余裕のある若年層には、コストパフォーマンスの高い選択となるでしょう。
ただし、将来的にライフステージが変化したときには見直しが必要です。