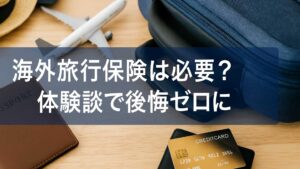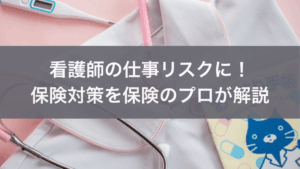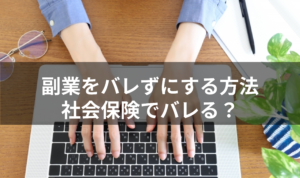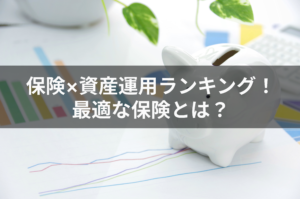ペットは大切な家族。でも、いざ病気やケガをしたとき、高額な治療費に戸惑った経験はありませんか?
近年、ペット保険の加入率がじわじわと上昇していますが、それでもまだ約2割ほど。
この記事では、最新の加入率やメリット・注意点、そしてこれからの選び方までをわかりやすく解説します。

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
日本のペット保険加入率はどれくらい?

これから「日本のペット保険加入率はどれくらい?」について解説します。
- 2024年時点の最新加入率データ
- 犬と猫、ペットの種類で異なる加入率の違い
それでは一つずつ解説していきます。
最新の加入率データとその推移
2024年の日本のペット保険加入率は、およそ20〜22%と報告されています。これはペット保険会社の公開資料や各種市場調査から得られた数値をもとにしています。
この数字は、10年前と比べて着実に上昇しており、年々“ペット保険に入っておくのが当たり前”という空気が広がっていることを示しています。
公益社団法人日本獣医師会やアニコム損保などの報告によれば、特に都市部では加入率が全国平均を上回る傾向が見られています。
ペットを家族の一員として捉える考え方が浸透し、いざというときの医療費に備える人が増えている証拠だといえるでしょう。
ここ10年でどれだけ加入者が増えた?
10年前(2014年)の加入率は、約6〜8%程度といわれていました。それに対して2024年時点では20%を超えており、3倍近くの伸びを見せています。
この背景には、以下のような要因が影響しています。
- 動物医療の高度化により、1回の診療費が高くなっている
- SNSやブログで「保険に助けられた」という体験談が増加
- 保険料の月額も以前よりバリエーションが増え、選びやすくなった
身近なところでも、「友人や家族にすすめられて保険に入った」という人が増えてきた実感があるかもしれません。
ペット保険は今や“意識の高い一部の人”だけのものではなく、“多くの飼い主が検討する選択肢”になってきています。
加入率が伸びている背景とは?
加入率が上がっている最大の理由は、「ペットは大切な家族」という意識の変化です。
少子高齢化や単身世帯の増加もあり、ペットとの暮らしが“心の支え”になっているケースも多く見られます。そうなると、万が一の備えとして保険の必要性を感じやすくなります。
また、保険会社が提供するアプリやLINE通知などのサービスが使いやすくなったことも、加入のハードルを下げる大きな要因となっています。
こうした流れの中で、「うちの子のために、いざというとき困らない準備をしておきたい」と考える飼い主が増えているのです。
犬のペット保険加入率は猫より高い?その理由
犬の保険加入率は、猫に比べて依然として高い傾向があります。
日本アニマル倶楽部の調査では、犬の加入率は30%前後に対し、猫は約20%程度にとどまっています。
理由としては、犬の方が外に出る機会が多く、ケガや事故のリスクが高いため。また、犬はしつけや医療ケアを重視する飼い主が多く、保険との相性が良い傾向があります。
散歩中の事故やドッグランでのトラブルなど、予期せぬトラブルに備えるために加入しておくケースが多く見られます。
猫のペット保険加入率が近年伸びている背景
ここ数年、猫の保険加入率が少しずつ上昇しています。理由のひとつは、室内飼育が主流になってきたことで“病気への意識”が高まっていることです。
猫は一見健康そうでも、実は腎臓疾患などの慢性病を抱えやすい動物です。通院が必要なケースも多く、費用がかさむため保険が心強い味方になります。
最近では「猫専用プラン」を打ち出す保険会社も増えており、ニーズに合わせた保険商品が整ってきたことも加入者増加の後押しとなっています。
小動物や鳥のペット保険事情は?犬猫以外の現状
犬や猫以外のペット、たとえばウサギ、ハムスター、インコなどについては、保険に加入できる商品自体が限られています。
一部の保険会社では小動物向けのプランも登場していますが、加入率は犬猫と比べて圧倒的に低く、まだ1%未満と推測されています。
ペット医療のインフラや診療体制も動物種によって異なるため、保険の普及には時間がかかると考えられています。
多頭飼い・高齢ペット世帯が注目されるワケ
最近では、高齢のペットを多頭飼いしている家庭の中で保険の必要性を感じるケースが増えています。
年をとると病気や通院の頻度が高くなるため、医療費の負担も一気に大きくなりやすいからです。
実際、動物病院で「この子もペット保険に入っておけばよかった…」という声が聞かれることも少なくありません。
複数のペットを飼っている場合には、コストと安心のバランスをとる選択として保険が注目されています。
なぜペット保険の加入率は上昇しているのか

これから「なぜペット保険の加入率は上昇しているのか」について解説します。
- ペット医療費の高額化
- ペットの高度医療や長寿化の進行による医療の現実
それでは一つずつ解説していきます。
動物病院の治療費はどれくらいかかる?
犬や猫の治療費は、想像以上に高額になることがあります。
ちょっとした診察やワクチンであれば数千円程度ですが、手術や入院が必要なケースでは10万円〜30万円以上かかることも珍しくありません。
アニコム損保の「家庭どうぶつ白書」によれば、犬の椎間板ヘルニアの手術は平均20万円以上、猫の尿路閉塞の治療も1回で数万円に達することがわかっています。
週に何度も通院が必要になると、交通費や薬代も含めて月5万円以上になるケースもあります。こうした現実に直面した飼い主が、「保険に入っておけばよかった…」と後悔することは少なくありません。
動物医療が高度化している今、治療費の負担は“もしも”ではなく、“いつか来るかもしれない日常”として備えるべき時代になっています。
高度医療や長寿化が進むペット医療の現状
現在のペット医療は、CTやMRI、内視鏡など人間とほとんど変わらないレベルまで進化しています。
それに伴って、治療費も比例して高額化しています。
また、ペットの寿命自体も延びており、犬・猫ともに平均寿命は15歳前後と言われています。
高齢になればなるほど、慢性疾患やがん、関節トラブルなど継続的な治療が必要になる病気が増えてきます。
慢性腎不全のような長期通院が必要な疾患にかかると、1年間で数十万円以上の医療費がかかることもあります。
長く健康で一緒に過ごしてもらうために、医療費の備えとして保険を活用する選択が広がってきているのです。
ペット保険に加入するメリット・加入しない理由

これから「ペット保険に加入するメリット・加入しない理由」について解説します。
- 加入するメリット:高額治療への備え・安心感
- 加入しない理由:費用負担・補償内容の不安
- 本当に必要?判断するためのチェックポイント
それでは一つずつ解説していきます。
万が一の病気やケガでも経済的に焦らなくて済む
突然のケガや病気に対して、費用面で迷わず対応できるのが保険の一番の強みです。
動物病院の診療は自由診療であるため、軽い処置でも数千円〜、手術ともなると10万〜30万円以上かかることもあります。
こうした高額な治療費が一度に発生したときに、保険に加入していれば費用の7割〜9割が補償され、自己負担が抑えられます。
友人のケースでは、愛犬が散歩中に車と接触して骨折。治療と入院費で約25万円かかりましたが、保険に加入していたため支払いは3万円ほどで済み、大きな安心につながったそうです。
経済的な不安がないことで、ペットにとって必要な治療をすぐに受けさせてあげられるのは、飼い主にとっても大きな心の支えになります。
長期通院・慢性疾患にも備えられる保険がある
病気は一度きりでは終わらず、長く通院が必要になるケースもあります。
特に腎臓病や糖尿病などの慢性疾患は、継続的な通院や薬の投与が求められ、1ヶ月に1万円以上かかることも珍しくありません。
最近では、こうした通院費や投薬費も対象にした通院重視型の保険商品も増えており「入院しなければ出ない」という時代から、日常的なケアにも対応できる内容に進化しています。
猫を飼っている知人は、腎不全の早期発見で週1通院が必要になりましたが、保険の通院補償のおかげで安心して治療を継続できたと話していました。
日常的な通院や再診が続くと、精神的・金銭的に疲れてしまいますが、保険がその一部を支えてくれることで継続しやすくなります。
心の余裕が生まれ「最善の治療」が選べる
保険に入っていると、治療費の心配をせずに「一番いい治療を受けさせてあげたい」という気持ちで動けます。
本来であれば選びたい検査や手術も、費用の心配から「もう少し様子を見ようか…」と先延ばしにしてしまうこともあります。
保険に加入していることで、選択肢の幅が広がり、ペットにとって最善の医療を選ぶことが可能になります。
ある飼い主さんは、がんの疑いでMRI検査を勧められた際に、保険が適用されたことで即決し、早期発見・早期治療に繋がったと話していました。
金銭的な制約が少ないことで迷わずベストな判断ができることは、ペットにも飼い主にも大きな安心につながります。
毎月のペット保険料が負担に感じる人が多い
ペット保険の平均的な保険料は月額2,000〜4,000円程度。これを「高い」と感じてしまう人も少なくありません。
特に若いペットや健康な子だと、「使わなかったらもったいない」と感じることもあるようです。また、多頭飼いしている場合はその分保険料が重なり、家計の負担感が増します。
飼い主の中には、あらかじめ毎月貯金をして備えるスタイルを選ぶ人もいますが、予想外の大きな出費にはやはり不安が残ります。
保険料が気になる方には、補償内容を絞ったリーズナブルなプランや、掛け捨て型の簡易保険を検討してみるのも選択肢のひとつです。
補償されないケースが意外と多い?注意点とは
すべての病気やケガが補償対象になるわけではない点は要注意です。
多くのペット保険では、既往症や先天性疾患、高齢での新規加入には制限がかかる場合があります。
また、予防接種やワクチン、ノミ・ダニ対策といった予防医療、避妊・去勢手術なども補償外となっていることが多いです。
「保険に入っているのに出なかった」というトラブルを避けるためには、事前に補償範囲をきちんと確認することが大切です。
加入する前に約款やFAQをしっかり読み込んでおくと、納得して選ぶことができるようになります。
ペットが若くて元気なうちは「もったいない」と思われがち
特に子犬・子猫の頃は病気のリスクが少なく、「今は必要ない」と感じる飼い主も多いようです。
実際に若くて元気な時期に大きな治療費がかかることは稀なため、保険料が無駄に思えてしまうのは自然なことかもしれません。
ただ、万が一の事故や急性疾患は年齢に関係なく起こりますし、保険は若いうちに入っておいた方が条件がよい(加入しやすく保険料も安い)という利点もあります。
「いざ必要になってからでは遅かった」という声も少なくないため、健康なうちから備えるという考え方もひとつです。
本当に必要?判断するためのチェックポイント
ペットが若くて健康なうちは必要性を感じにくいかもしれませんが、体質や遺伝的な要素、病歴によってリスクは大きく変わります。
特定の犬種(フレンチブルドッグや柴犬など)は、皮膚病や呼吸器トラブルを起こしやすく、早期からの備えが重要です。
すでに病気歴がある場合、加入できない・条件が付く可能性もあるため、判断は早めの方がよいでしょう。
健康診断の結果をもとに検討することで、自分のペットに合った補償が必要かどうかが見えてきます。
自分の経済状況と治療費のリスクバランス
「いざというときに、すぐに数万円〜十数万円出せるか?」という問いに対して、迷いがある場合は保険加入を検討しておくと安心です。
急な入院や手術が重なると、短期間で数十万円規模の出費になることもあります。毎月の保険料と比べて、どちらが現実的かを天秤にかけるのがポイントです。
貯金で対応できる場合もありますが、突発的な医療費が生活を圧迫する可能性があるなら、保険は「安心代」として検討する価値があります。
今後の加入率はどうなる?ペット保険の未来

これから「今後の加入率はどうなる?ペット保険の未来」について解説します。
- 市場規模の拡大と加入率の見通し
- 保険会社が取り組むサービス向上と差別化
- 飼い主が知っておきたい今後の選択肢
それでは一つずつ解説していきます。
市場規模の拡大と加入率の見通し
日本のペット関連市場は、近年ますます拡大しています。
矢野経済研究所の調査によると、2023年の国内ペット市場規模は1兆6,000億円を超えており、今後も右肩上がりの成長が見込まれています。
この中でペット保険が占める割合も年々増えており、「食費」や「トイレ用品」と同じく“定常支出”として定着しつつあります。
近年は高齢化・単身世帯の増加により、「万が一に備える」意識がペットにも向けられるようになり、保険の需要は確実に伸びてきています。
日々の暮らしの中で、ペットが“生きがい”や“家族の中心”になっている人にとって、保険は必要不可欠なサービスになりつつあるのです。
ペット保険加入率は今後どう推移する?専門家の予測
現在、日本のペット保険加入率は約20%前後ですが、今後5年以内に30%超え、2030年頃には40%に届く可能性もあると見られています。
背景には、デジタル技術の進化や、保険商品の多様化、さらに飼い主のライフスタイルの変化があります。
動物病院の電子カルテやアプリ連携により、保険利用の利便性が上がっていることも後押ししています。
業界紙やマーケットレポートでは、「現在の3人に1人が加入を検討している」という調査結果もあり、成長余地はまだまだ大きいといえます。
今後は、加入率の上昇とともに「どう選ぶか」がより重要になる時代が来るでしょう。
高齢ペット・多頭飼育世帯の増加が市場を後押し
ペットの寿命が延びていることや、1世帯あたりの飼育頭数が増加傾向にあることが、今後の保険市場の拡大をさらに後押ししています。
高齢ペットは通院頻度や医療費が増えるため、保険に入っておく意義が高まり、また多頭飼い家庭では「1匹目で後悔したから、2匹目からは保険に加入した」という声も多くなっています。
このように、経験を通じて保険の価値を実感した飼い主が増えていくことで、市場の拡大は今後も続いていくと予測されます。
ペット保険会社が取り組むサービス向上と差別化
保険会社の中には、従来の「一律プラン」ではなく、通院のみ・手術のみなど、ニーズに応じて内容を選べるカスタマイズ型の保険を提供するところが増えてきています。
飼い主の経済状況やペットの健康状態に合わせて、「いま必要な補償だけ」を選べることで、無駄なく備えられる点が好評です。
また、「1歳までは最低限の補償で」「シニア期からはしっかりカバー」といった年齢に応じた設計が可能な保険も登場しており、加入しやすさが格段にアップしています。
この柔軟性は、今後ますます重要視されるポイントになっていきそうです。
ペット健康管理との連携による「予防型」保険の登場
新たなトレンドとして注目されているのが、「予防型」のペット保険です。
これは、単に病気やケガに備えるだけでなく、健康診断やフィットネスアプリとの連携により病気を未然に防ぐことを目的としています。
一部の保険会社では、体重や活動量を記録することで保険料が割引になるなど、“予防することで得をする”設計が始まっています。
このように保険が“病気になる前のケア”にまで踏み込むことで、ペットのQOL(生活の質)を高めるサポートへと進化しつつあります。
保険が「万が一」だけでなく「日々の健康づくり」にも活用される時代が、すぐそこまで来ています。
ペット保険以外にも選べる“備え”の方法
保険に加入しない選択肢として、「毎月決まった額をペット貯金に回す」「医療費共済制度を活用する」といった方法もあります。
自治体や動物病院によっては、予防医療や緊急治療の一部をサポートする制度が用意されていることもあり、こうした情報も知っておくと役に立ちます。
また、ペットクラブや会員制度によって割引を受けられるサービスなども、うまく使えば保険の代わりになる場面があります。
保険はひとつの手段にすぎません。自分に合った“備え方”を探すことが大切です。
ペット保険に頼らない?積立や共済との比較
積立型の備えは、自由に使える反面、大きな出費に対応しにくいというデメリットがあります。
一方、共済型の仕組みは掛け金が安い反面、補償が限定的な場合も多いです。
保険との大きな違いは「予測できない高額な出費」にどれだけ備えられるか。
保険はそのリスクに対する備えに強みがあるため、積立や共済とは役割が異なります。
それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、自分の家計や飼育スタイルに合ったバランスを見極めることが重要です。
変化するペット保険市場で損をしないための情報収集法
ペット保険は今、商品数・補償内容・価格帯のすべてが多様化しています。
だからこそ、「なんとなく」で選んでしまうと、いざというときに補償が受けられなかったというリスクもあります。
比較サイトや口コミだけでなく、保険会社の公式サイト、獣医師の意見など、複数の情報源からのチェックが大切です。
また、ペットの年齢や健康状態によっては加入条件が変わることもあるため、検討は“早め”が鉄則です。
正しい情報をタイムリーに得ることで、後悔しない選択ができるようになります。
よくあるQ&A
Q1. 日本のペット保険加入率は、なぜまだ20%程度と低いのでしょうか?
A. 理由の一つは、「高い」「補償内容がわかりにくい」といった不安が根強いことです。
また、自由診療で料金が病院によって異なるため、保険の適用範囲が不透明に感じられる点も敬遠される理由となっています。
ただし、近年はアプリ対応やプランの多様化が進み、加入のハードルは下がりつつあります。
Q2. ペット保険って本当に必要?健康なうちから入る意味はある?
A. 健康なうちだからこそ入りやすく、保険料も安く抑えられるのがポイントです。
高齢になると持病や既往歴で加入が難しくなることもあります。
急なケガや病気はいつ起こるかわからないため、早いうちから備えることで、将来的な安心に繋がります。
Q3. ペット保険以外で医療費に備える方法はありますか?
A. はい、月々の積立やペット医療共済制度を利用する方法もあります。
また、動物病院の会員制度や定期健診パックを活用することで、予防医療のコストを抑える工夫も可能です。
保険は選択肢の一つとして、自分のライフスタイルに合った備え方を見つけることが大切です。
ペット保険の加入率 まとめ
日本のペット保険加入率は年々上昇しており、背景には医療費の高騰やペットの家族化があります。
特に高齢ペットや多頭飼い世帯では、保険のニーズが高まりつつあります。
これからはペット保険の加入率のさらなる伸びとともに、飼い主自身が柔軟な備え方を選ぶ時代です。
ペット保険について気軽に相談したい方、見積もりを試してみたい方は、どんな小さな疑問でも大歓迎です。
お気軽に下記からご連絡くださいね。