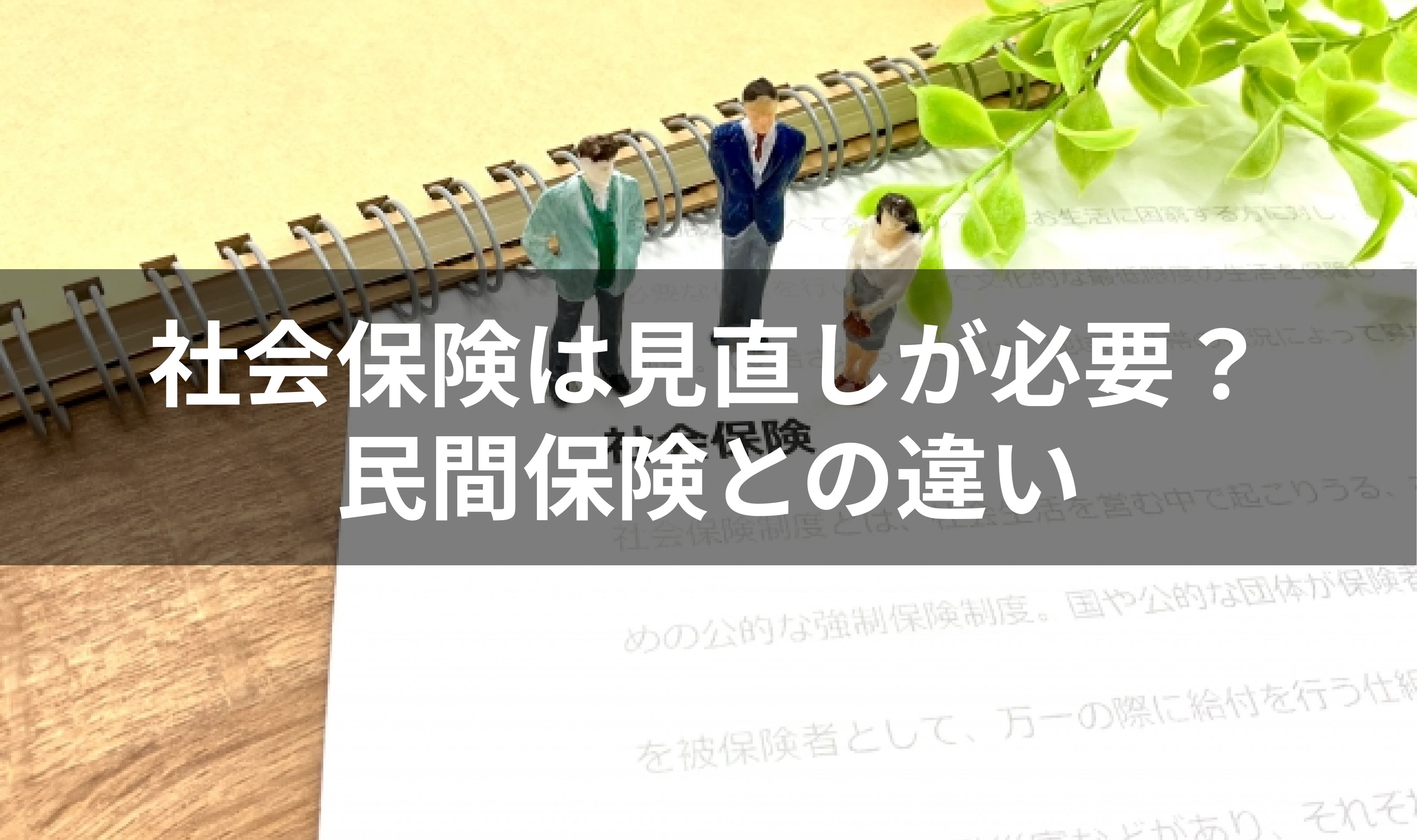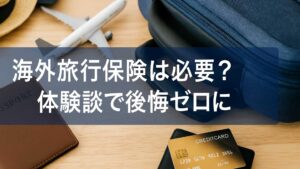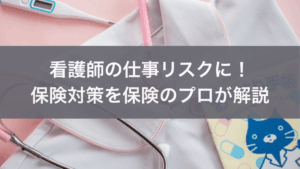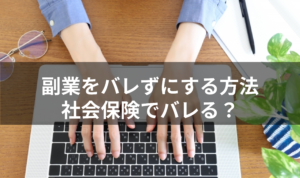社会保険に見直しは必要か、会社員とフリーランスの社会保険の違いとは、生命保険は社会保険に含まれるのか…。
社会保険は必要だとわかっていても、疑問が多いですよね。
この記事では、気になる社会保険に関する疑問を解決し、あなたに必要な社会保険の保障についてわかりやすく解説します。
最後までご覧いただくと「社会保険と民間保険の違い」「ライフステージで見直しが必要な保険」「社会保険の加入における注意点」が簡単に分かるようになります。
- 社会保険と民間保険とは?
- ライフステージによって見直しが必要な保険?
- 雇用形態別の社会保険の違い

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
社会保険とは?
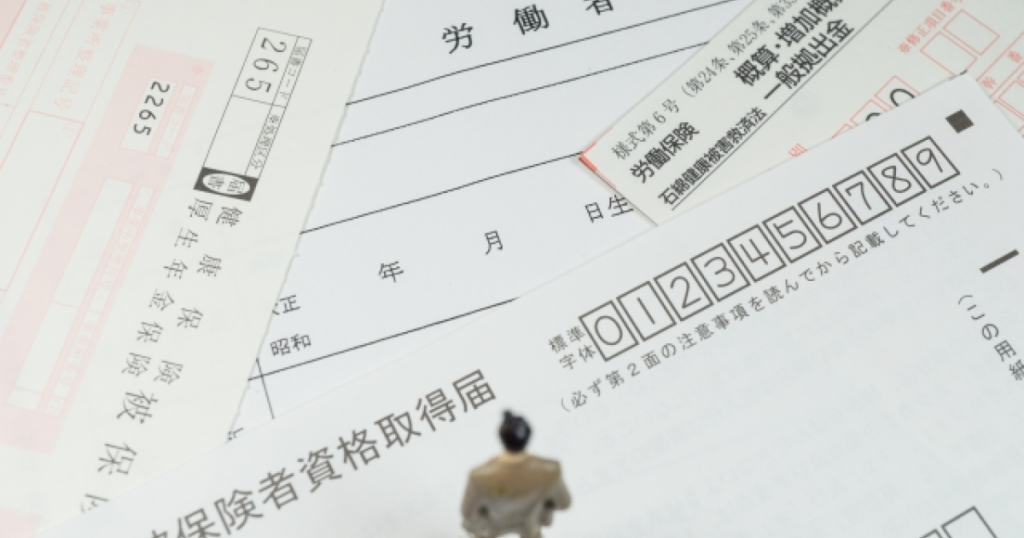
社会保険とは、国が設けた公的な保険制度で、すべての労働者に加入の義務があります。
医療費、失業時の生活費や老後の生活資金などのリスクに備えることができる制度です。
社会保険の定義
社会保険は、働く人々を対象に病気や事故、老後の生活をサポートするための、国の公的な保険制度です。
社会保険への加入は義務であり、収入に応じた社会保険の保険料が支払われます。
社会保険は社会全体で負担を分け合う仕組みとなっており、予測不能な事態に対応できるため、国民の生活の安定に寄与しています。
社会保険の内容や社会保険の保険料は法律で決まっているため、個人が自分で見直す必要はありません。
会社に勤務している場合、社会保険料は給与から天引きされる形で自動的に支払われており、その内容も法律に基づいています。
社会保険は主に以下の5つの保険が含まれます。
- 健康保険: 医療費の一部負担
- 年金保険: 老後の生活費支援
- 雇用保険: 失業時の給付
- 介護保険: 高齢期の介護サポート
- 労災保険: 仕事上の事故に対応
この中でも重要である健康保険、年金保険、雇用保険が三大社会保険と呼ばれています。
会社員が病気で入院した際は、健康保険が医療費の負担を軽減し、退職後は年金保険が老後の生活を支えます。
また、失業した場合は雇用保険が生活費を支援するなど、生活全般をカバーします。
社会保険は、生活のリスクに備えるために必要な保障を提供し、すべての労働者にとって不可欠な制度です。
社会保険が必要な理由
社会保険は、予測できない病気や事故、失業、老後などの生活のリスクから個人と家族を守るために必要です。
社会保険は働く人々が生活を支えるために、十分な保障を受けられるように設計されています。
とくに、病気や怪我、失業などの不測の事態に直面した場合、金銭的な負担を軽減するために社会保険は必須です。
日本の健康保険では医療費の自己負担が最大3割となっており、大きな医療費がかかる場合でも経済的負担が軽減されます。
社会保険は、生活におけるリスクに対応し、経済的負担を軽減するために必要不可欠な保障を提供します。
社会保険と民間保険の違い
社会保険は基本的な保障を提供し、民間保険はそれを補完する形でより手厚い保障を提供します。
- 社会保険
会社員は社会保険に強制的に加入。年金、健康保険、雇用保険などに加入する義務がある - 民間保険
自営業者やフリーランスは社会保険に加入しない場合がある。民間の医療保険や年金保険への加入が推奨される
会社員にとって社会保険は強制加入であるため、基礎的な保障を提供する役割を果たします。
一方、民間保険は選択的に加入するもので、より多くの保障や特典を提供します。
民間保険は、社会保険でカバーできない部分を補うために役立ちます。
民間保険にはさまざまな種類がありますが、以下が代表的です。
| 民間保険 | 例 | 内容 |
|---|---|---|
| 医療保険 | がん保険、入院日額保障保険、手術費用保険 | 医療費をカバー。とくに入院や手術費用の負担を軽減 |
| 生命保険 | 定期保険、終身保険、収入保障保険 | 死亡時や重病時に遺族に給付金を支払う。保障内容は多岐にわたる |
| がん保険 | がん診断一時金保険、がん治療給付金保険 | がん治療にかかる費用をカバー。がん診断を受けた際に給付金あり |
| 傷害保険 | 事故によるケガや障害に対する保障 | 事故でのケガや障害による治療費、休業保障を提供 |
| 個人年金保険 | 定額年金、変額年金 | 老後の資金を積み立て、年金を支給する保険 |
社会保険と民間保険:保険料の負担の違い
社会保険の保険料は、労働者の収入に基づいて算出されるため、収入が多いほど社会保険料が高くなります。
会社員の場合、社会保険の保険料の一部は企業が負担し、残りは個人が支払います。
また、社会保険の保険料は一律の率であるため、負担が公平に分かれます。
民間保険は、保障内容や加入条件によって保険料が異なり、高額な保険料を支払う場合もあります。
| 項目 | 社会保険 | 民間保険 |
|---|---|---|
| 月額保険料 | 約4万5,000円(会社負担分含む) | 1万円〜5万円以上(保障内容による) |
| 保障内容 | 健康保険、年金、介護保険などの基本的な保障 | 医療保険や生命保険などの追加保障 |
| 保険の対象 | 主に病気や事故、年金支給など | 入院費、手術費用、死亡保険など |
| 会社負担の有無 | 会社が半分負担(健康保険、年金) | すべて自己負担 |
社会保険は収入に基づく安定した負担となり、企業負担分もあるため比較的負担が軽いです。
民間保険は保障内容によって保険料が大きく異なります。
社会保険と民間保険:保障内容の違い
社会保険の保障内容は、基本的な生活リスク(病気、事故、老後など)に対応するものに限られています。
例えば、健康保険では病気やケガの治療費を一部カバーしますが、高額な治療費には限界があります。
一方、民間保険は、社会保険でカバーされない部分を補完する役割を果たし、より広範囲な保障を提供します。
| 項目 | 社会保険(健康保険の場合) | 民間保険(医療保険の場合) |
|---|---|---|
| 自己負担割合 | 医療費の3割 | 契約によって異なるが、自己負担が少ない |
| 入院・治療費 | 自己負担は3割 | 補償内容によっては自己負担ゼロも |
| 高額な治療費 | 高額療養費制度で上限あり | 補償額が高ければ自己負担少なく済む |
社会保険は基本的な保障を提供し、民間保険はその補完を行います。
社会保険と民間保険を活用することで、さらに安心した生活が実現できます。
見直しの必要がある保険とは
生活の変化やライフステージに応じて、定期的に保険を見直すことが重要です。
社会保険については給与から自動的に天引きされるため、個人で見直す必要がありません。
とくに見直しが必要なのは、以下の民間保険が挙げられます。
- 生命保険
- 医療保険
生命保険は、結婚や子供の誕生によって家族の生活保障が変わるため見直しが必要です。
例えば、配偶者や子どもを被保険者に追加したり、保障額を増やすことを考えると良いでしょう。
医療保険は、年齢と共に健康リスクが高まるため、より手厚い医療保障への切り替えを検討する必要があります。
加入後に健康状態が変わった場合も保障内容の変更を考慮しましょう。
保険は定期的に見直し、ライフスタイルや健康状態に合わせて調整することが大切です。
これにより、無駄な支出を避け、最適な保障を受けることができます。
雇用形態別!社会保険の加入について
社会保険の加入:会社員の場合
会社員は、就職時に自動的に社会保険に加入します。
企業が社会保険の手続きを代行し、給料から社会保険の保険料が差し引かれます。
雇用保険、健康保険、年金保険、介護保険などの各種社会保険が適用され、給与から自動的に引き落としされます。
- 月収30万円の場合
健康保険、年金保険、介護保険などの社会保険料が合計で月額4万5,000円が差し引かれる
会社員は、社会保険に自動的に加入し、給与から社会保険の保険料が差し引かれるため手続きが簡単で負担が少なくて済みます。
社会保険の加入:自営業者の場合
自営業者は、原則として国民健康保険や国民年金に加入しますが、希望により社会保険への加入も可能です。
自営業者は、企業に勤務していないため、強制的な社会保険への加入義務はありません。
ただし、事業規模や従業員数が多い場合、厚生年金に加入することも可能です。
- 自営業者が従業員を雇っている場合
厚生年金と健康保険の加入が必要 - 従業員がいない場合
国民健康保険と国民年金に加入し、保険料は自分で支払う
自営業者は基本的に国民保険に加入しますが、事業形態により社会保険に加入することもできます。
社会保険への加入方法は、事業内容や規模によって異なります。
社会保険の加入:フリーランスの場合
フリーランスも基本的には国民健康保険や国民年金に加入しますが、仕事の内容や収入に応じて選択肢があります。
会社員のように社会保険の加入義務はないため、自分で保険を選び、加入する必要があります。
国民健康保険と国民年金が基本ですが、年収が一定額以上(基本130万円以上)の場合には、任意で社会保険に加入することも可能です。
- 例えば年収300万円の場合
国民健康保険と国民年金の合計で月に約3万円程度が支払われる - 年収が一定額以上(基本130万円以上)の場合
社会保険に加入することも可能
フリーランスは、国民健康保険と国民年金に加入するのが基本ですが、収入状況や仕事の内容に応じて、社会保険に加入することもできます。
配偶者の社会保険加入について
配偶者が社会保険に加入している場合、あなたがその配偶者の扶養に入ることができる場合があります。
一般的に配偶者が健康保険や年金の加入者である場合、扶養に入ることでご自身が社会保険に加入しなくて済むこともあります。
配偶者の扶養に入る条件
配偶者が会社員の場合、扶養に入るためには収入が一定額以下であることが必要です。
扶養に入るための収入基準は、年間収入が130万円未満であることが求められます。
これを超える場合は、配偶者として社会保険に加入し、社会保険の保険料を支払う必要があります。
- 年収が130万円未満の場合
配偶者の扶養に入ることができる - 年収が130万円を超える
配偶者の扶養を外れ、自分で社会保険に加入する必要がある
配偶者が扶養に入るためには、年収が130万円未満であることが条件です。
社会保険の加入:配偶者が会社員の場合
配偶者が会社員の場合、会社での社会保険に加入しているため、基本的には追加の手続きは不要です。
会社員の場合、社会保険への加入は企業の責任であり、雇用契約時に手続きが行われます。
そのため、配偶者が会社員であれば、扶養に入るか独立して加入するかを選ぶ必要があります。
配偶者が会社員の場合、社会保険には自動的に加入され、必要な社会保険の手続きは企業が行うため特別な手続きは不要です。
配偶者が自営業者の場合の加入方法
配偶者が自営業者の場合、社会保険には加入しないため、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
自営業者は企業に所属していないため、社会保険に加入しません。
代わりに国民健康保険や国民年金に加入し、必要に応じて扶養に入るか独立して加入するかを選びます。
- 扶養に入る条件を満たしている場合
家計を助けるために扶養に入ることができる
※年収が一定額(130万以上)を超えると、独自に保険料を支払う必要がある
配偶者が自営業者の場合、社会保険に加入することはできず、国民健康保険や国民年金に加入し、扶養の条件を確認することが必要です。
社会保険加入時の注意点

社会保険に加入する際には、社会保険の手続き方法や対象外費用などを理解しておくことが重要です。
とくに、自分に必要な社会保険の保障内容を確認し、免責額や自己負担額について把握しておくことが、より適切な選択をするために不可欠です。
また、社会保険と民間保険の併用についても理解しておくべきポイントです。
自分に必要な社会保険の保障内容の確認
自分に必要な社会保険の保障内容を確認するためには、まず生活環境やライフスタイルを分析し、どの社会保険の保障が最も重要かを把握することが大切です。
社会保険には健康保険、年金保険など、さまざまな種類がありますが、どの社会保険の保障が最も必要かは年齢や家族構成などによって異なります。
例えば、家族が多い場合は医療費負担を軽減するために健康保険の利用が重要になります。
自分に必要な社会保険の保障内容を確認するには、ライフスタイルや将来のリスクをしっかりと考え、どの社会保険の保障が最も必要かを把握することが重要です。
免責額や自己負担額を理解する
社会保険に加入する際、免責額や自己負担額を理解しておくことは、予想外の費用負担を避けるために不可欠です。
免責額や自己負担額とは、保険が適用される際に自己負担しなければならない金額です。
社会保険の場合、自己負担額は一般的に医療費の一部負担で、病院での治療費や薬代がその例です。
例えば、健康保険では、診療費の3割を自己負担することになりますが、限度額を超える場合には高額療養費制度を利用できます。
免責額や自己負担額についてしっかり理解し、とくに高額な治療が必要になった場合の対応策(高額療養費制度など)を事前に把握しておくことが重要です。
社会保険と民間保険の併用について
社会保険と民間保険を併用することで、より広範囲な保障を確保することが可能です。
ただし、社会保険と民間保険の併用時には過剰な保障に繋がらないように注意が必要です。
社会保険は基本的な保障を提供しますが、医療費や老後の生活費など、すべてのリスクに対応できるわけではありません。
民間保険を併用することで、社会保険の保障を補完し、より手厚い保障を確保できます。
しかし、過剰な保険をかけてしまうと、無駄な支払いが発生する可能性もあるため、どの保障が重複しているのかを確認することが重要です。
社会保険と民間保険を併用する際は、保障内容をよく確認し、重複や過剰な保障を避けることが大切です。
まとめ
社会保険は、病気や事故、老後の生活費など、さまざまなリスクに備えるための公的保険制度です。
民間保険は、社会保険の基礎的な保障を補完する形で選択可することができます。
社会保険と民間保険を併用することで、より手厚い保障を得られます。
また、ライフスタイルや家族構成の変化に応じて、民間保険の見直しが必要です。
保険について気軽に相談したい方、見積もりを試してみたい方は、どんな小さな疑問でも大歓迎です。
お気軽に下記からご連絡くださいね。