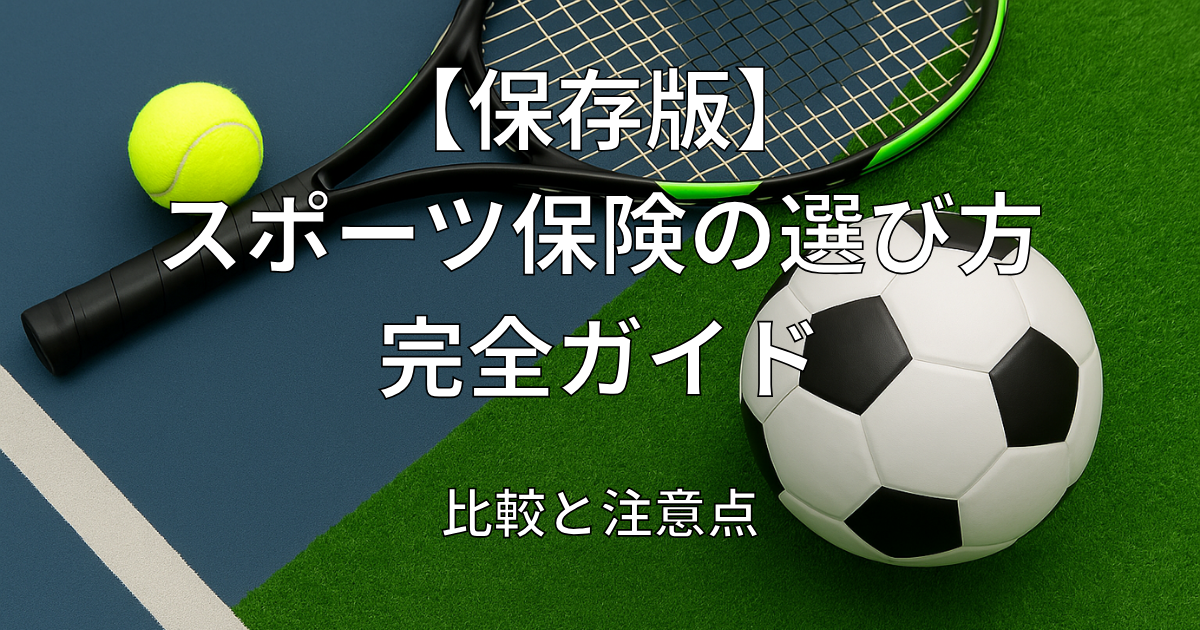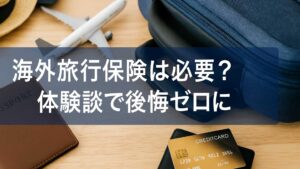「週末のサッカー、仕事帰りのジム、お子さんの部活動…。大好きなスポーツを楽しんでいる時
ふと「もし大きなケガをしたら…」「保険って色々あるけど、正直どれが自分に合ってるのか分からない」なんて不安を感じたことはありませんか?
この記事は、そんなあなたのための「スポーツ保険の選び方 完全ガイド」です。
ケガにかかる費用や補償内容の基本はもちろん、個人・団体、1日・年間の違い、保険金が支払われない注意点まで、知っておくべき全知識を凝縮しました。
もう保険選びで迷う必要はありません。
自分と大切な人を守る最適なお守りを見つけて、お金やケガの心配をせず、安心してプレーに集中しましょう!

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
もしかして他人事?スポーツに潜むリスクと保険の必要性

スポーツを安全に楽しむためには、万が一のリスクに備えることがとても大切です。
この章では、スポーツに潜む具体的なリスクと、なぜ保険が必要なのかについて解説します。
- そのケガ、数万円の出費に…スポーツで起こりがちな事故と費用
- 人気スポーツ別!よくあるケガと治療期間の目安(サッカー・野球・テニス・ランニング等)
- 治療費だけじゃない!通院交通費やサポーター代など見えない出費
それでは一つずつ解説します。
そのケガ、数万円の出費に…スポーツで起こりがちな事故と費用
スポーツ中の骨折で手術や入院が必要になると、たとえ健康保険が適用されても、自己負担額が数十万円にのぼる可能性があります。
「まさか自分が」と思っていても、スポーツにケガはつきものです。
公的な医療保険制度があるため医療費の全額を負担することはありませんが、それでも高額な出費になるケースは少なくありません。
特に、入院中の食事代や、より快適な環境を求めた場合の差額ベッド代などは、健康保険の適用外となり全額自己負担となります。
また、高額な医療費がかかった際に自己負担額を一定に抑える「高額療養費制度」がありますが、それでも一般的な所得の方で月々8万円以上の負担は覚悟しなくてはなりません。
週末の社会人サッカーを楽しんでいた30代のAさんは、試合中に相手と激しく接触し、足首を骨折してしまいました。
救急車で運ばれ、緊急手術を受けることに。
手術と10日間の入院でかかった医療費の総額は約80万円。
健康保険(3割負担)と高額療養費制度を利用しても、最終的な自己負担額は約10万円になりました。
さらに、差額ベッド代や入院中の雑費で3万円が別途かかり、退院後のリハビリ通院費も継続的に発生しています。
このように、一度のケガがきっかけで、予期せぬ大きな経済的負担が発生する可能性があります。
好きなスポーツを安心して続けるためにも、こうしたリスクを事前に理解しておくことが重要です。
人気スポーツ別!よくあるケガと治療期間の目安(サッカー・野球・テニス・ランニング等)
あなたが楽しんでいるスポーツによって、起こりやすいケガの種類や、プレーに復帰できるまでの期間は大きく異なります。
スポーツの種類ごとに体の使い方が違うため、当然ながらケガをしやすい部位や種類も変わってきます。
相手と接触するコンタクトスポーツでは突発的なケガが多く、個人競技では同じ動作の繰り返しによる体の特定部位への負担がケガにつながる傾向があります。
▼人気スポーツ別の主なケガと治療期間の目安
| スポーツの種類 | よくあるケガ | 治療期間の目安(軽度〜重度) |
| サッカー・フットサル | 捻挫、肉離れ、打撲、前十字靭帯損傷 | 2週間 〜 8ヶ月以上 |
| 野球 | 肩・肘の障害(野球肘)、肉離れ、突き指 | 3週間 〜 6ヶ月以上 |
| テニス・バドミントン | 肘の障害(テニス肘)、手首の腱鞘炎、アキレス腱断裂 | 3週間 〜 6ヶ月以上 |
| ランニング・マラソン | 足底筋膜炎、腸脛靭帯炎(ランナー膝)シンスプリント | 1ヶ月 〜 4ヶ月以上 |
| バスケットボール | 突き指、捻挫、膝の靭帯損傷、アキレス腱断裂 | 2週間 〜 8ヶ月以上 |
※治療期間はあくまで目安であり、個人差や重症度によって変動します。
あるテニス愛好家の方は、長年悩まされていた「テニス肘」の痛みが悪化し、数ヶ月間ラケットを握れなくなってしまいました。
また、市民ランナーの方が、大会に向けて練習量を増やした結果「ランナー膝」を発症し、整形外科でのリハビリを余儀なくされるケースも頻繁に耳にします。
サッカーやバスケでは、ジャンプの着地や方向転換の際に膝の靭帯を損傷し、手術と長期のリハビリが必要になることも珍しくありません。
ご自身のプレーするスポーツにどんなリスクが潜んでいるのかを把握し、万が一ケガをした場合にどれくらいの期間、プレーや日常生活に影響が出るのかをイメージしておくことが、適切な備えの第一歩となります。
治療費だけじゃない!通院交通費やサポーター代など見えない出費
スポーツでケガをした際の出費は、病院の窓口で支払う治療費や薬代だけではありません。
実は、それ以外にも様々な「見えない費用」が発生します。
ケガの治療が長引けば、その分だけ見えない出費もかさんでいきます。
自宅から遠い専門病院へ通うことになれば交通費はかさみますし、松葉杖やサポーター、テーピングといった治療を補助するアイテムの購入費も必要です。
これらは基本的に自己負担となるため、積み重なると家計への意外な負担となり得ます。
大学の部活動で膝を痛めてしまったBさんは、週に3回のリハビリ通院を命じられました。
片道500円の電車賃が、1ヶ月で約6,000円の出費に。
さらに、医師の指示で購入した膝用の高機能サポーターは1万円近くしました。
アルバイトのシフトを減らさざるを得なかったこともあり、治療費以外の出費が想像以上に痛手となったそうです。
治療に専念するためにも、こうした直接的な治療費以外の出費までカバーできる備えがあると、より安心して治療に臨むことができます。
スポーツ保険の中には、こうした諸費用まで手厚くサポートしてくれるものもあります。
まずは基本から!スポーツ保険の「?」を解決

スポーツ保険と聞くと、「ケガをした時の保険」というイメージが強いかもしれませんが、実はそれだけではありません。
現代のスポーツ保険は、プレーヤーを取り巻く様々なリスクに対応できるよう、補償内容がとても充実しています。
これから、スポーツ保険がカバーする主な補償内容について詳しく解説していきます。
- 【自分のため】傷害保険金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)
- 「個人向け」と「団体向け」メリット・デメリット
- 保険金が支払われない?知っておきたい対象外のケース
それでは一つずつ解説します。
【自分のため】傷害保険金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)
スポーツ保険の最も基本となる補償が、ご自身のケガに直接備えるための「傷害保険金」です。
万が一の死亡時から日々の通院まで、ケガの程度に応じた保険金が支払われる、まさに保険の中核部分です。
この傷害保険金は、ケガの状態によって主に以下の4つに分類されます。
| 保険金の種類 | 支払われるケース | 支払われ方のイメージ |
| 死亡保険金 | スポーツ中の事故が原因で死亡した場合 | 契約した保険金額の全額 |
| 後遺障害保険金 | ケガが原因で体に障害が残った場合 | 障害の程度(等級)に応じて保険金額の数%〜100% |
| 入院保険金 | ケガの治療で入院した場合 | 「入院1日あたり 〇円」 |
| 手術保険金 | ケガの治療で手術を受けた場合 | 「入院保険金日額の 〇倍」など |
| 通院保険金 | ケガの治療で通院した場合 | 「通院1日あたり 〇円」 |
社会人サッカーチームに所属するAさんは、試合中に相手と接触した際に膝をひねり、前十字靭帯を断裂する大ケガを負ってしまいました。
手術と2週間の入院、その後半年にわたるリハビリ通院が必要と診断されます。
Aさんが加入していたスポーツ保険からは、まず入院日数に応じた「入院保険金」、そして手術内容に応じた「手術保険金」が支払われました。
さらに、退院後のリハビリ通院に対しても、通院日数分の「通院保険金」が支払われ、治療費の大きな助けとなりました。
このように、傷害保険金はケガによる直接的な経済的負担を様々な角度からサポートしてくれます。
スポーツ保険を選ぶ際には、まずこの基本補償がご自身の活動レベルに見合っているかを確認することが大切です。
【相手のため】個人賠償責任補償(モノを壊した・人にケガをさせた)
スポーツ中に誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりした場合の「損害賠償」に備えるのが、個人賠償責任補償です。
自分だけでなく、相手への責任を果たすためにも非常に重要な補償です。
スポーツに夢中になっていると、周りへの注意が散漫になる瞬間もあります。
そんな時に起こるのが「対人事故」や「対物事故」です。
過去には数千万円にもおよぶ高額な賠償命令が出た判例もあり、決して他人事ではありません。
この補償があれば、万が一加害者になってしまった場合に、相手への治療費や慰謝料、壊してしまったモノの修理代などを保険金でまかなうことができます。
さらに、当事者同士では解決が難しい示談交渉を、保険会社が代行してくれる「示談交渉サービス」が付いているプランも多く、精神的な負担を大きく軽減してくれます。
ゴルフの練習場で打ったボールが大きく逸れ、隣のホールにいた人のカートに直撃。窓ガラスを割ってしまったとします。
修理費用は十数万円。
当事者同士の話し合いでは気まずい空気が流れてしまうかもしれません。
しかし、保険に加入していれば、すぐに保険会社に連絡することで、後の対応はすべてプロに任せることができます。
保険会社が相手方と修理費用の支払いについて交渉を進めてくれるため、あなたは安心して練習に集中できます。
個人賠償責任補償は、高額な賠償リスクからあなた自身と家族を守るだけでなく、万が一のトラブルの際に円満な解決をサポートしてくれる、非常に心強いお守りとなる補償です。
【盗難・破損に】携行品損害補償(ラケットやウェアなど)
スポーツをするために持ち出していたご自身の持ち物(携行品)が、偶然の事故で盗まれたり、壊れてしまったりした際の損害を補償してくれるのが「携行品損害補償」です。
大切な道具を守るための、嬉しいプラスアルファの補償です。
この補償の対象となるのは、自宅の外へ持ち出している身の回り品です。
スポーツ用品で言えば、ゴルフクラブやラケット、スキー・スノーボードの板、ウェアなどが該当します。
ただし、スマートフォンやノートパソコン、現金、クレジットカードなど、補償の対象外となるものも定められているため、事前の確認が必要です。
また、保険金から自己負担額(免責金額)として数千円が差し引かれて支払われるのが一般的です。
テニスの大会に出場したCさんは、試合後にロッカールームへ戻ると、置いていたはずのラケットバッグが見当たりませんでした。
中には愛用のラケット2本と、おろしたばかりのシューズが入っていました。
すぐに警察へ盗難届を提出し、保険会社へ連絡。
後日、保険金が支払われたことで、新しい用具を揃える費用負担を大きく軽減することができました。
特に高価なスポーツ用品を使っている方にとっては、万が一の盗難や破損は経済的にも精神的にも大きな痛手となります。
この携行品損害補償は、そんな悲しい出来事の際のダメージを和らげてくれる、頼れる味方です。
「個人向け」と「団体向け」メリット・デメリット
スポーツ保険には、自分で選んで加入する「個人向け」と、チームや団体でまとめて加入する「団体向け」の2つのタイプがあります。
個人向けのスポーツ保険は、補償内容を自分のニーズに合わせて自由にカスタマイズできるのが最大の魅力ですが、その分、団体向けに比べると保険料が割高になる傾向があります。
保険は、加入者が多いほど一人ひとりのリスクが分散されるため、保険料を安く設定できます。
個人向け保険は、一人ひとりのリスクに合わせて契約を結ぶため、どうしても団体契約のようなスケールメリットは働きにくくなります。
しかしその分、数多くの保険会社や商品の中から、補償額や特約などを比較検討し、「自分だけの保険」をオーダーメイド感覚で組み立てられるという大きな利点があります。
▼個人向け保険のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 補償内容や保険金額を自由に選べる | 団体向けに比べて保険料が割高なことが多い |
| チーム活動外の個人練習などもカバーできる | 自分で情報を集めて比較検討する手間がかかる |
| スポーツの種類を問わないプランが多い | ー |
登山とサイクリングが趣味のAさんは、遭難時の救援者費用や、高価な自転車の盗難にも備えたいと考えていました。
所属しているサイクリングチームの団体保険ではそこまでカバーされていなかったため、複数の保険会社の商品を比較。
結果、基本のケガの補償に加えて、「救援者費用補償」と「携行品損害補償」を手厚くした個人向けプランに加入しました。
年間の保険料は団体保険よりも高くなりましたが、自分の活動スタイルにぴったり合った安心感を得ることができました。
このように個人向け保険は、保険料よりも「自分に必要な補償をしっかり確保したい」と考える方に適した選択肢と言えます。
【団体向け】メリット・デメリット(割安だが補償が画一的)
団体向けのスポーツ保険は、なんといっても手頃な保険料で加入できるのが魅力です。
一方で、補償内容はチーム全員で共通のため、個人の希望を反映させることはできません。
チームや協会といった団体単位で大勢がまとめて加入するため、「団体割引」が適用され、一人あたりの保険料が安く抑えられています。
保険会社としても事務手続きを効率化できるため、その分が保険料に反映される仕組みです。
補償内容は、その団体の活動内容に合わせて標準的なものがパッケージ化されているため、個人で保険を選ぶ手間が省けるという手軽さもあります。
▼団体向け保険のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 保険料が個人向けに比べて非常に割安 | 補償内容や金額を個人で選べない |
| 加入手続きが簡単(チームでまとめてくれる) | チーム活動中以外の事故は補償されないことが多い |
| ー | 補償額が十分でない場合がある |
多くの少年スポーツチームや社会人サークルが利用している「スポーツ安全協会」の保険は、まさにこの団体向け保険の代表例です。
年間2,000円以下の掛金で、傷害補償と賠償責任補償といった基本的な内容がセットになっています。
ただし、補償されるのはあくまで「団体の管理下における活動中」に限られるため、チーム活動外での自主練習中のケガなどは対象外となる点には注意が必要です。
コストを抑えつつ、活動に最低限必要な基本的な補償を手軽に確保したい場合には、団体向け保険が非常に合理的な選択肢となります。
保険金が支払われない?知っておきたい対象外のケース
スポーツ保険は非常に頼りになる存在ですが、残念ながらどんなケースでも保険金が支払われるわけではありません。
「こんなはずじゃなかった…」とならないために、あらかじめ保険金が支払われない代表的なケースをしっかり理解しておくことが重要です。
スポーツ保険(正しくは傷害保険)から保険金が支払われるのは、そのケガの原因が「急激・偶然・外来」の3つの条件をすべて満たす「事故」である場合のみです。
これが保険金支払いの大原則となります。
なぜなら、スポーツ保険は予測できない突発的な出来事による損害を補償するための制度だからです。
この3つの条件は、その「予測できない突発的な出来事」を定義するための、いわば物差しのようなものです。
| 条件 | 意味 | 具体例 |
| ① 急激 | 突発的に発生し、ケガまでの時間的な間隔がないこと | 突然ボールが飛んできて当たった |
| ② 偶然 | 予期できず、ケガをするつもりがなかったこと | グラウンドで足をもつらせて転んだ |
| ③ 外来 | ケガの原因が体の外部からの作用によること | 相手選手と接触した |
サッカーの試合中、相手選手と接触して転倒し、腕を骨折してしまったとします。
この場合、①相手との接触は突発的(急激)で、②骨折することは予期していなかった(偶然)ものであり、③接触という体の外からの力が原因(外来)です。
このため、3つの条件をすべて満たし、保険金の支払い対象となります。
この「急激・偶然・外来」という3つのキーワードは、保険金を請求できるかどうかを判断する上での最も基本的な考え方です。
ご自身のケガがこの条件に当てはまるかどうか、冷静に考えてみることが大切です。
疲労骨折や野球肘など、繰り返しによる「スポーツ障害」はなぜダメ?
長期間にわたるトレーニングの積み重ねによって発生する「疲労骨折」や「野球肘」「テニス肘」といった、いわゆる「スポーツ障害」は、原則としてスポーツ保険の補償対象外となります。
これらの症状は、特定の動作を繰り返すこと(オーバーユース)によって、体の特定部位に徐々に負担が蓄積して起こるものです。
つまり、突発的に起こる「急激」な事故とは言えず、体の内部から時間をかけて発生するものなので「外来」の条件にも当てはまらない、と判断されるためです。
性質としては「ケガ」というよりも「病気」に近い扱いになります。
熱心なランナーが、毎日の走り込みによって徐々にすねに痛みを感じ始め、病院で診てもらったところ「シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)」と診断されたとします。
これは日々の練習の積み重ねが原因であり、ある日突然起こった事故ではありません。
そのため、残念ながらスポーツ保険の対象とはなりません。
同じスポーツ活動中の痛みでも、突発的な事故による「ケガ(傷害)」なのか、練習の積み重ねによる「障害(疾病)」なのかによって、保険の扱いは大きく変わります。
この違いを理解しておくことが重要です。
ピッケルを使う山岳登山、ハンググライダーなどの危険なスポーツ
一般的なスポーツ保険では、特に危険度が高いと分類されるスポーツは、あらかじめ補償の対象外(免責事項)として定められています。
ご自身の行うスポーツがこれに該当しないか、事前の確認が不可欠です。
保険は、加入者全体でリスクを公平に負担し合う「相互扶助」の精神で成り立っています。
そのため、他と比べて著しくリスクが高い活動を同じ条件で補償すると、公平性が保てなくなってしまいます。
そのため、保険会社はあらかじめ約款で「対象外となるスポーツ」を具体的に定めているのです。
- 山岳登山(ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用するもの)
- スカイダイビング、ハンググライダー
- ボブスレー、リュージュ
- 自動車、モーターボートによる競技や試運転 など
秋に紅葉を楽しむためのハイキングで転んでケガをした場合は、多くの場合補償の対象となります。
しかし、冬に同じ山へピッケルやアイゼンを装備して本格的な雪山登山に臨み、滑落してケガをした場合は対象外となる可能性が高いです。
このような活動を行う際は、そのリスクに対応した専用の「山岳保険」などに別途加入する必要があります。
ご自身の活動が、契約する保険の補償対象にきちんと含まれているか、パンフレットや約款の「保険金をお支払いできない主な場合」といった項目を必ずチェックするようにしましょう。
後悔しない!自分にぴったりのスポーツ保険を見つけるステップ

ここからはいよいよ本題です。
自分に合った保険を選ぶための最初のステップは、あなたが行うスポーツにどんなリスクが潜んでいるかを知り、それに合わせて優先すべき補償を見極めることです。
スポーツの種類によって、ケガのしやすさや必要な備えは大きく異なります。
- あなたのスポーツは?危険度に応じた補償を選ぼう
- 「1日」「年間」あなたに合う加入期間は?
それでは一つずつ解説します。
あなたのスポーツは?危険度に応じた補償を選ぼう
ラグビー、サッカー、柔道、バスケットボールといった選手同士の接触が避けられないコンタクトスポーツでは、骨折や靭帯損傷など、入院や手術、長期の通院を伴う大きなケガのリスクが高いため、入院・通院補償を手厚く設定することが重要です。
これらのスポーツは、プレーの性質上、他者との激しい衝突や転倒が頻繁に起こります。
スポーツ振興センターの給付データを見ても、学校管理下での死亡・障害事例では、柔道やラグビーといったコンタクトスポーツが上位を占めることがあり、そのリスクの高さがうかがえます。
そのため、万が一の際に治療に専念できるよう、経済的な基盤となる入院・通院時の補償を充実させておくのが賢明です。
社会人ラグビーチームに所属するAさんは、試合中にタックルを受けた際に肩を脱臼し、手術と入院を余儀なくされました。
幸いにも、彼は入院1日あたり10,000円、通院1日あたり5,000円という手厚い補償の個人保険に加入していました。
おかげで、治療費の心配をすることなくリハビリに集中でき、仕事の欠勤による収入減もカバーすることができました。
激しいプレーが魅力のコンタクトスポーツを心から楽しむためにも、万が一のケガで治療が長引いても生活に困らないよう、入院・通院補償の日額を高めに設定しておくことを強くおすすめします。
個人競技(ランニング・ゴルフ等)は賠償責任と自分のケガのバランスを
ランニング、ゴルフ、テニス、水泳といった個人競技では、自分のケガに備える傷害補償と、他人に損害を与えてしまう可能性に備える賠償責任補償の両方を、バランス良く確保することが大切です。
個人競技は他者との接触は少ないものの、同じ動作の繰り返しによる体の故障(スポーツ障害とは別の突発的なケガ)や、転倒などのリスクは常に存在します。
一方で、ゴルフの打球が人に当たったり、ランニング中に歩行者とぶつかってケガをさせてしまったりといった、意図せぬ加害事故の可能性もゼロではありません。
自分のため、そして相手のため、両方のリスクを想定しておく必要があります。
趣味でゴルフを楽しんでいるBさんは、練習場で打ったボールが予期せず大きく曲がり、隣の打席にいた人のキャディバッグに直撃。相手の高級ドライバーを傷つけてしまいました。
幸い、個人賠償責任補償が付いた保険に入っていたため、修理費用を保険で対応することができました。
また、別の日には無理なスイングで腰を痛めてしまい、数回の通院を余儀なくされましたが、こちらも通院補償でカバーできたのです。
個人競技を長く楽しむためには、ご自身の体を守るための傷害補償と、他者への責任を果たすための賠償責任補償という、2つの柱をしっかりと立てておくことが賢明な選択と言えるでしょう。
自然が相手(スキー・登山等)なら救援者費用特約は必須
スキー、スノーボード、登山、トレイルランニングなど、雄大な自然の中で行うスポーツを楽しむ方は、通常のケガの補償に加えて、遭難時の捜索・救助費用をカバーする「救援者費用補償」を必ず付けておくべきです。
山やゲレンデでは、天候の急変や道迷い、滑落といった予測不能な事態が起こり得ます。
万が一、自力で下山できなくなり救助を要請した場合、民間の救助隊やヘリコプターが出動すると、その費用は数百万円にのぼることも珍しくありません。
この高額な費用は全額自己負担となるため、救援者費用補償はまさに「命綱」とも言える重要な備えです。
友人と数人でバックカントリースキーを楽しんでいたCさん。
天候が急変して猛吹雪となり、視界を失いコースを見失ってしまいました。
自力での行動は危険と判断し、スマートフォンで救助を要請。
駆けつけた民間の山岳救助隊によって無事救助されましたが、後日、捜索費用として100万円近い請求書が届きました。
しかし、事前に救援者費用補償が付いた保険に加入していたおかげで、この高額な費用を自己負担なく支払うことができました。
自然の中で活動するスポーツでは、通常のケガのリスクとは別に、「遭難」という特有のリスクが存在します。
このもしもの事態に備える救援者費用補償は、絶対に外せない必須の特約だと心得ておきましょう。
「1日」「年間」あなたに合う加入期間は?
スポーツをするのが、年に数回の特定のイベントや友人とのレジャーに限られているのであれば、その都度加入できる1日・短期保険が最も合理的で無駄のない選択です。
年間保険は、定期的な活動を前提に保険料が設定されています。
年に1〜2回しか活動しないのに年間の保険料を支払うのは、少しもったいないですよね。
その点、1日保険は数百円からという手頃な価格で加入でき、必要な時だけピンポイントでリスクに備えられます。
スマートフォンを使えば、当日でも思い立った時にすぐ申し込める手軽さも大きな魅力です。
普段は運動をしないけれど、年に一度だけ学生時代の仲間と集まってフットサル大会に参加しているAさん。
彼にとって、年間のスポーツ保険は必要ありません。
大会当日の朝、会場へ向かう電車の中でスマートフォンからサッと1日保険に申し込むのが、ここ数年の恒例になっています。
昨年、その大会で軽い捻挫をしてしまいましたが、保険に入っていたおかげで治療費を心配することなく病院へ行くことができ、改めてその手軽さとありがたみを実感したそうです。
あなたにとってスポーツが「非日常の特別なイベント」であるならば、1日・短期保険は「必要な時だけ、必要な分だけ」という、非常に賢い備え方と言えるでしょう。
どっちがお得?年間利用回数で考える保険料の損益分岐点
1日保険と年間保険、どちらがお得になるかの境目(損益分岐点)は、年間の活動回数でおおよその判断がつきます。
一般的には、年に5〜7回以上スポーツをするなら、年間保険の方が割安になることが多いと言われています。
どちらがお得かを知るには、簡単な割り算をするだけです。あなたが検討している保険プランで、実際に計算してみましょう。
年間保険料 ÷ 1日保険料 = 年間保険の方がお得になる年間の活動回数
スキーが趣味のCさんは、シーズン中に何回ゲレンデに行くかを考えてみました。
最低でも月に2回、3ヶ月間は通うので、合計6回は滑りに行く計算です。
1日タイプのスキー保険は1回700円ほどなので、6回で4,200円かかります。
一方で、同じような補償内容の年間保険を調べてみると、年間4,000円のプランを見つけました。
これなら年間保険の方がお得で、シーズン最初の申し込み忘れの心配もありません。さらに、夏に楽しむハイキングも補償対象になると知り、迷わず年間保険を選びました。
「年間保険料 ÷ 1日保険料」という簡単な計算で、あなたにとってどちらの選択が経済的かが見えてきます。ぜひ一度、ご自身の活動計画と照らし合わせて試算してみてください。。
まとめ:最適なスポーツ保険で、もっと自由に、もっと安全に!
スポーツに潜むケガや高額な賠償リスク、知っていますか?
「どの保険を選べばいいの?」と悩むあなたのために、保険の基本から知っておくべき全知識をこの記事に凝縮しました。
自分に合う補償の見極め方、1日保険と年間保険の使い分けもこれで完璧です。
正しい知識であなたに最適な「お守り」を見つけ、もうケガを恐れないで!
弊社ではスポーツ保険は取り扱っていませんが、今回はスポーツ保険についてご紹介させていただきました。