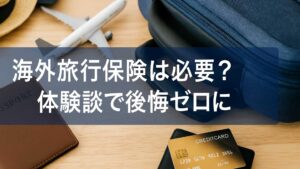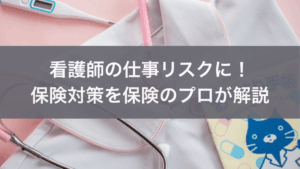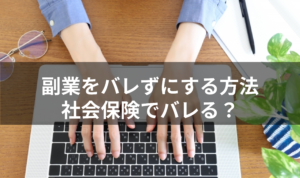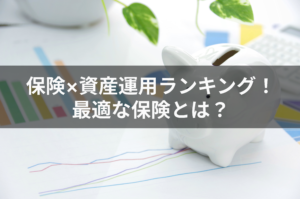「うちの子に保険って必要かな?」そう思ったことはありませんか?
突然のケガや病気で高額な治療費がかかることもある一方で、「使わなかったら損かも…」と迷う気持ちもわかります。
この記事では、ペット保険のメリット・デメリットや実際の医療費データをもとに、あなたと愛犬・愛猫にとって本当に必要かどうかを一緒に考えていきます。

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
ペット保険は必要?不要?その答えとは

これから「ペット保険は本当に必要なのか?」「逆に、入らなくてもいいケースは?」という疑問にお答えしていきます。
- 思わぬ高額治療費に備えられる安心感
- ペットの治療内容を選ぶ幅が広がる(手術・通院など)
- 賠償責任特約や電話相談などの付帯サービスが使える
- ペット保険料が掛け捨てで「もったいない」と感じる人も多い
- 貯金や自己負担で十分に備えられる人もいる
それでは一つずつ解説していきます。
思わぬ高額治療費に備えられる安心感
ペットも人と同じように、突然の病気やケガで入院や手術が必要になることがあり、数十万円単位の医療費がかかるケースも少なくありません。
アニコム損保の調査によると、ペットの1回の手術費用は平均で犬が約14万円、猫が約12万円前後。
重度の病気では20万円を超えることもあります。
また、複数回の通院が必要な場合は、年間で数十万円規模の出費になることもあります。
動物病院でのレントゲンやMRI検査、入院費、麻酔などはすべて自己負担になるため、いざというときに金銭的な準備ができていないと治療を先延ばしにせざるを得ない状況にもなりかねません。
保険に入っておくことで、予期せぬ医療費にも落ち着いて対応できるという安心感が生まれます。
金銭的な備えがあることで、飼い主としても余裕をもってペットの治療に向き合えるはずです。
ペットの治療内容を選ぶ幅が広がる(手術・通院など)
保険に入っていることで、治療方法の選択肢が広がるのも大きなメリットのひとつです。
動物医療は年々高度化しており、MRI検査や内視鏡手術など、精密で体に優しい治療法も増えています。
しかし、こうした先進医療は高額になりがちで、費用だけで治療方法を決めなければならない状況に陥ることもあります。
ペット保険に加入していれば、こうした高額治療にも前向きにチャレンジしやすくなり、飼い主として最善の治療を選ぶ余地が広がります。
「本当はこっちの方が負担が少ない治療なんだけど…」と悩むのではなく、「ベストな治療を選べる」という選択肢の広さは、保険の恩恵のひとつと言えるでしょう。
賠償責任特約や電話相談などの付帯サービスが使える
最近のペット保険には、医療費の補償だけでなく日常のトラブルや不安をサポートしてくれるサービスも充実しています。
たとえば、「賠償責任特約」付きの保険では、散歩中に他人や他の犬にケガをさせてしまった場合などに備えられます。
また、獣医師や看護師に24時間相談できる電話サービスがついている保険もあり、「ちょっとした不調だけど病院に行くべきか迷う」といった時にとても頼りになります。
こうした付帯サービスは、金銭的な補償以外にも心の支えとなる要素。とくに初めてペットを飼う人にとっては、安心感を高めてくれる存在になります。
ペット保険料が掛け捨てで「もったいない」と感じる人も多い
ペット保険の多くは、毎月支払う保険料が掛け捨てとなっています。
そのため、1年間でほとんど病院に行かなかった場合、「何も使わなかったのに損したかも…」と感じる人も少なくありません。
特に若くて健康なペットの場合は、1年間に数回の軽い通院だけというケースも多く、「自分で払った方が安かったかも」という印象を受けるのも無理はありません。
保険は“備え”としての性格が強いため、「使わなかった=健康だった」というポジティブな見方もできますが、それでも「使わなかった保険料が戻ってこない」という点に納得できない人には向かないかもしれません。
貯金や自己負担で十分に備えられる人もいる
すでに「ペット用の医療費貯金」をしっかり確保している、あるいは毎月の生活費に余裕があり、高額治療にも自己負担で対応できるという人であれば、必ずしも保険に加入する必要はないかもしれません。
実際に、「保険料を支払う代わりに毎月一定額をペット用貯金に回している」という飼い主さんもいます。
中には、10万円〜20万円の医療費にも即対応できるよう備えている人も。
経済的な見通しが立っていて、計画的に備えができるのであれば、保険に頼らずとも安心してペットと向き合うことができます。
ペット保険のメリット・デメリットとは

これから「ペット保険のメリット・デメリット」について解説します。
- 通院費用も補償される保険なら継続治療にも安心
- ペット保険があることで獣医師と相談しながら最適な治療を選べる
- 窓口精算が可能な保険なら支払いの手間も軽減
- 多頭飼い・シニア犬向けの特約や割引制度も活用できる
- ワクチン・避妊手術などの予防医療は対象外になることが多い
- 持病や先天性疾患が補償対象外になるケースに注意
- 加入年齢に制限があり、高齢ペットは対象外の場合も
- ペットの年齢が上がると保険料も上昇し、割高に感じやすい
それでは一つずつ解説していきます。
通院費用も補償される保険なら継続治療にも安心
慢性疾患やアレルギー体質など、こまめな通院が必要な場合、費用がかさんでいくのが現実です。
通院補償のある保険を選ぶことで、治療を途中で諦めずに済みます。
一般社団法人ペットフード協会の資料によれば、犬の通院1回あたりの平均は約5,200円、猫は約4,600円。
月に3回通えば、それだけで1万5,000円近い出費になります。
アトピー性皮膚炎で月2〜3回通院しているミニチュアダックスフンドでは、年間の通院費が約12万円に達しましたが、通院補償のある保険により自己負担は4万円以下で済んでいます。
継続的な治療が必要なとき、金銭的な不安が治療の妨げにならない環境をつくれるのは、ペットにも飼い主にもやさしい選択です。
ペット保険があることで獣医師と相談しながら最適な治療を選べる
医療費の心配があると、「本当に必要な治療かどうか」を慎重になりすぎてしまい、結果的に治療の質を落としてしまうことがあります。
先進的な治療法や、より身体への負担が少ない方法は、コストが高い場合が多く、自己負担だけだと選びにくいのが現実です。
保険に加入していれば、費用よりも効果や安全性を優先して治療を選びやすくなります。
膝の脱臼で手術を検討していたトイプードルでは、3種類の治療法が提示され、そのうち一番高額な術式(約28万円)を選択しました。
保険で補償されたことで、満足度の高い治療が受けられたとのことです。
獣医師と相談のうえで、妥協のない治療を選べる環境をつくることが、保険の大きな役割のひとつです。
窓口精算が可能な保険なら支払いの手間も軽減
診察のたびに一度全額を支払い、あとから書類を提出して保険金を請求するという手順は、意外と手間に感じるもの。
そんな中、「窓口精算」ができる保険は便利さが際立ちます。
窓口精算対応の保険であれば、動物病院でその場で補償額が差し引かれ、自己負担分だけを支払えばOK。
時間的にも心理的にも負担が減ります。
シニア犬を介護中の飼い主さんは、週に2〜3回病院に通っていたため、書類の提出が煩雑で困っていました。
窓口精算対応の保険に切り替えたことで、通院がスムーズになり、看護の時間に専念できるようになったと話しています。
通院頻度が多いペットには、利便性の高さも重要な判断基準になります。
多頭飼い・シニア犬向けの特約や割引制度も活用できる
ペット保険には、家庭のスタイルに応じた特約や割引が用意されていることがあり、工夫次第でお得に備えることができます。
代表的なものに「多頭割引(2頭目から保険料10%OFF)」や「シニア特約(年齢による補償延長)」があります。
これにより、複数のペットを飼っている家庭でも保険料を抑えることが可能です。
14歳の猫と5歳の犬を飼う家庭では、2頭とも同じ保険会社で契約したことで、年間約8,000円の割引を受けられたとのこと。
さらに、シニア猫にも対応した特約により、万が一の備えも確保できました。
家族構成やペットの年齢に合わせた保険の活用が、コスト面・安心面の両立につながります。
ワクチン・避妊手術などの予防医療は対象外になることが多い
ペット保険では、治療目的ではない予防医療については補償の対象外とされるケースが一般的です。
以下のような処置は補償されないことが多くあります。
| 対象外になるケース | 主な理由 |
| ワクチン接種 | 予防目的であるため |
| 避妊・去勢手術 | 計画的な選択であり、医療リスクが低いため |
| 歯石除去・スケーリング | 美容や予防目的と見なされることが多い |
「ワクチンで体調を崩して病院へ行ったが、補償されなかった」といった声も聞かれます
加入前に対象外項目をよく確認しておくことが大切です。
健康維持のための施術が意外と対象外になっていることは、見落としやすい注意点です。
持病や先天性疾患が補償対象外になるケースに注意
ペット保険では、契約時点で既に発症している病気や先天性の疾患については補償対象外とされることがあります。
たとえば「てんかん」や「股関節形成不全」などは、生まれつきや若いうちに診断されやすいため保険加入時に告知義務が発生し、対象外と判断されるケースも。
保険会社によっては病名ごとに補償の有無が異なるため、事前に診断歴がある場合は、各社の約款をよく比較する必要があります。
先天性の心疾患がある猫を飼っている家庭では、3社に相談したところ、2社は補償対象外、1社は追加条件付きで加入可能という結果になりました。
持病がある場合は「入れる保険」と「補償される内容」をよく精査することが重要です。
加入年齢に制限があり、高齢ペットは対象外の場合も
ペット保険には「新規加入できる年齢の上限」が設けられている場合が多く、高齢のペットはそもそも保険に入れない可能性があります。
一般的には「満10歳未満まで」が加入条件の目安。
これを超えると、新規契約自体が受け付けられなくなることもあります。
12歳の柴犬を飼っている家庭では、保険を検討したものの、複数社で「加入対象外」となり、結局保険に入ることができなかったそうです。
「今は元気だからまだいいかな」と先送りしていると、いつの間にか加入できない年齢になってしまうこともあります。
検討は早めが安心です。
ペットの年齢が上がると保険料も上昇し、割高に感じやすい
ペット保険の保険料は、年齢とともに段階的に上がることが一般的です。
若いうちは月額1,000円台でも、10歳を超えると3,000〜5,000円以上になることもあります。
保険会社の料金表を見ると、7歳以降で急激に保険料が上がる設計が多く、「年齢=リスク増」として保険料に反映されています。
11歳のミニチュアシュナウザーを飼っている家庭では、若い頃に1,800円だった保険料が、現在は月4,500円近くまで上昇しており、家計の負担として重く感じるようになったそうです。
高齢期は医療費がかかる反面、保険料も高額になるため、支出バランスを見ながらの判断が求められます。
実際にどのくらい医療費がかかる?

これから「ペットにかかる実際の医療費と、保険の利用状況」について解説します。
- 犬の椎間板ヘルニア手術:20〜40万円の出費例
- 猫の尿石症・腎不全など慢性疾患の継続治療費
- ガンや心臓病など重篤な病気は年間50万円超も
- 通院1回あたりの費用相場と頻度のリアル
- 年間医療費の平均額は犬で約5〜7万円、猫で約4〜6万円
- 実際に保険を使った人の割合(年間請求率)は約7割
- 請求が多い傷病ランキング:犬は皮膚炎・下痢、猫は膀胱炎など
- ペット保険利用者の満足度は「金額の安心感」と「使いやすさ」で分かれる
それでは一つずつ解説していきます。
犬の椎間板ヘルニア手術:20〜40万円の出費例
椎間板ヘルニアは特にミニチュアダックスフンドに多く見られる病気で、手術をともなうと非常に高額になることがあります。
アニコム損保などのデータでは、手術費用は軽度で20万円前後、重度では40万円を超えることも。
さらにMRI検査や入院を含めれば50万円近くかかる例もあります。
3歳のミニチュアダックスが突然歩けなくなり、精密検査と手術、5日間の入院を含めて総額42万円。
ペット保険に加入していたことで、約7割が補償され、自己負担は13万円ほどに抑えられました。
突然の高額治療に備えるには、保険の存在が非常に心強いです。
猫の尿石症・腎不全など慢性疾患の継続治療費
猫に多い病気として知られる尿石症や慢性腎不全は、一度発症すると長期的な治療が必要になります。
JAHA(日本動物病院協会)の調査によると、慢性腎不全の治療にかかる年間費用は15〜25万円前後。
点滴や血液検査、内服薬などが継続的に必要となるため、治療費がかさみがちです。
15歳の老猫が腎不全と診断され、月に2〜3回の通院と薬の処方により、年間で22万円近い支出に。
保険による補償で約14万円がカバーされ、経済的な負担は大幅に軽減されました。
慢性疾患と向き合う飼い主にとって、保険は治療継続の支えになります。
ガンや心臓病など重篤な病気は年間50万円超も
ペットの高齢化にともない増加しているのが、悪性腫瘍(ガン)や心臓病といった重篤な疾患です。
アニコムの統計や動物医療センターのデータによれば、これらの病気では年間50万円以上の出費が発生することも少なくありません。
特にガンの場合、手術・抗がん剤・放射線治療などを行うと100万円を超えるケースもあります。
9歳の柴犬が悪性腫瘍と診断され、化学療法や手術、通院を1年間続けた結果、総額で約60万円の医療費が発生しました。
保険がなければ治療継続を躊躇した可能性があったといいます。
命に関わる病気だからこそ、金銭的な備えが選択肢を広げてくれます。
通院1回あたりの費用相場と頻度のリアル
日常のちょっとした体調不良でも、動物病院への通院は重なれば大きな出費になります。
アニコム損保の「家庭どうぶつ白書2023」によると、通院1回あたりの費用は以下のとおりです。
| ペットの種類 | 平均費用(1回) |
| 犬 | 約5,200円 |
| 猫 | 約4,600円 |
月に1〜2回通院するケースでは、年間5〜10万円ほどの支出になることも。
軽症でも頻繁な通院が必要な持病があると、コストは無視できません。
アレルギー体質のフレンチブルドッグでは、毎月3回の通院で、3か月間の医療費が約5万円にのぼった例があります。
地味に感じる通院費も、蓄積すると大きな家計負担となります。
年間医療費の平均額は犬で約5〜7万円、猫で約4〜6万円
年間でかかる医療費の平均値を見ると、多くの飼い主がある程度の出費をしていることが分かります。
アニコム損保のデータでは、平均的な年間医療費は以下のとおり。
| ペットの種類 | 年間医療費平均 |
| 犬 | 約5〜7万円 |
| 猫 | 約4〜6万円 |
これは軽い病気も含めた平均値ですが、持病や高齢になるとこの金額を上回ることも珍しくありません。
10歳のトイプードルでは、アレルギー治療・耳のトラブル・予防接種の副反応などで年間6万5千円の出費が発生しました。
予期しない出費をカバーする選択肢として保険の検討も始めているそうです。
1年あたりの出費目安を把握しておくことで、保険料とのバランスも考えやすくなります。
ペット保険請求率
保険は「使わなかったら損」というイメージもありますが、実際には多くの人が1年のうちに何らかの形で保険を利用しています。
アニコム損保の統計によると、年間に1回以上の請求をした加入者はおよそ7割にのぼります。
8歳のキャバリアを飼っている家庭では、皮膚炎・膀胱炎・耳の炎症と複数回の通院があり、年間5回の保険請求を行いました。
結果として、支払った保険料よりも高い補償を受けられたそうです。
保険は「備え」ではあるものの、実際に使う頻度が高い点も見逃せません。
請求が多い傷病ランキング:犬は皮膚炎・下痢、猫は膀胱炎など
ペット保険の請求内容を見てみると、意外にも「重い病気」ではなく、日常的な症状のほうが多くなっています。
アニコムの「家庭どうぶつ白書2023」によると、主な傷病は以下の通りです。
- 皮膚炎
- 外耳炎
- 下痢
- 嘔吐
- 異物誤飲
- 膀胱炎
- 嘔吐
- 下痢
- 外耳炎
- 結膜炎
1歳の猫を飼っている家庭では、膀胱炎と結膜炎で年に3回通院しすべて保険で補償されました。
軽い症状でも気軽に病院に行ける環境が助かったと話しています。
よくある病気こそ、保険が活躍するシーンが多いのです。
ペット保険利用者の満足度は「金額の安心感」と「使いやすさ」で分かれる
ペット保険に満足している飼い主が多い一方で、「使いにくさ」を感じる人もいます。
満足度の分かれ目は、補償内容と利便性です。
- 高額治療に備えられて安心できた
- 窓口精算が使えて手間が少なかった
- よくある病気でも補償対象だった
- 保険金請求の手続きが面倒
- 補償対象外が多くて思ったより使えなかった
5歳の猫を飼う女性は、電話相談やLINEでの獣医相談が便利で安心感を得られていると話しています。
一方、別の飼い主は「手続きの煩雑さで使うのが億劫になった」と語っていました。
保険選びでは、「補償内容」と同じくらい「使いやすさ」も大切な判断軸になります。
あなたにとってペット保険は本当に必要?判断のための視点

これから「ペット保険が本当に必要かどうかを判断するための視点」について解説します。
- 「急な出費に備えたい人」はペット保険で安心を得られる
- 「毎年定期的に健康診断を受けている人」はペット保険不要派も
- 「複数頭を飼っている人」はコスパを見極めて判断
それでは一つずつ解説していきます。
「急な出費に備えたい人」はペット保険で安心を得られる
ペットの病気やケガは予告なく突然やってきます。
そのときに、すぐに数万円〜数十万円の出費が可能かどうかは大きな分かれ道になります。
アニコム損保のデータによると、犬の手術費用は平均で約14万円、入院費は1日あたり1万円前後という報告もあり、短期間で20万円以上の請求になることも珍しくありません。
一人暮らしの会社員が飼っているトイプードルが誤飲事故で緊急手術を受け、支払い総額が30万円を超えましたが、保険によって70%が補償されました。
手持ちがなくても安心して治療できたことに感謝しているそうです。
貯金に不安がある人ほど、こうした突発的な支出に備える保険の価値を感じやすいでしょう。
「毎年定期的に健康診断を受けている人」はペット保険不要派も
普段から健康管理を徹底していて、病気の早期発見・予防ができている人は、「保険より貯蓄で備える」という選択も十分にあり得ます。
日本獣医師会の提唱する年1回の定期健診を実践している家庭では、病気の重症化を防げる傾向が高いとされています。
健康診断を毎年欠かさず受けているシニア犬では、10年間でほとんど大きな病気がなく、保険に入らず自費で対応した方が支出が少なかったというケースもあります。
予防と貯蓄の組み合わせによるリスク分散も、保険に頼らない選択肢の一つです。
「複数頭を飼っている人」はコスパを見極めて判断
多頭飼いの家庭では、1匹ごとの保険料負担が大きくなりがちです。
そのため「全頭加入か、一部だけか」を慎重に検討する必要があります。
ペット保険会社によっては「多頭割引」を用意しているところもありますが、それでも3頭以上になると年間10万円を超える出費になることも。
犬2匹・猫1匹を飼っている家庭では、1匹だけ保険に加入し、他の子は“医療費積立”で備える方法を選んでいました。
結果的に無理のないバランスを保てたとのことです。
多頭飼いでは、保険と自費の併用を含めたコスパ重視の判断が求められます。
よくある質問(Q&A)
Q1:ペット保険って本当に必要?うちの子はまだ若くて元気なんだけど…
A:若いうちの加入こそ、保険の恩恵を受けやすいタイミングです。
年齢が上がると保険料は高くなり、持病があると加入できないこともあります。
元気な今だからこそ、無理なく備えができるチャンスです。
特に突然のケガや誤飲などは若い子でも起こりやすく、思わぬ出費の軽減に役立ちます。
Q2:ペット保険に入っても使わなかったら損じゃないですか?
A:使わなかったこと自体が「健康だった証」とも言えます。
確かにペット保険は掛け捨てが基本ですが、アニコムの統計では加入者の約7割が年1回以上保険請求をしています。
安心を買う」という考え方に納得できるかどうかが、加入判断のポイントになります。
Q3:ペット保険料が高くて悩んでいます。少しでもお得にする方法はありますか?
A:多頭割引や必要な補償を選ぶことで無理のない保険設計が可能です。
すべての補償をフルに付けなくても、自分のニーズに合ったプランを選べば保険料を抑えることができます。
また、複数頭を飼っている方は多頭割引や一部のみの加入なども検討の余地があります。
まとめ
ペット保険は「安心の備え」として心強い存在ですが、費用や補償範囲を正しく理解することが大切です。
高額な手術費用や慢性疾患の通院コストに備える手段として、多くの飼い主に選ばれています。
一方で、年齢制限や補償対象外の点に注意が必要です。
加入のメリット・デメリットを踏まえ、自分とペットのライフスタイルに合うかを見極めましょう。
- ペット保険の必要性やメリット・デメリットをわかりやすく整理
- 実際の医療費や請求データから加入判断の材料を提供
- あなたのライフスタイルに合った選び方と注意点を丁寧に解説
ペット保険について気軽に相談したい方、見積もりを試してみたい方は、どんな小さな疑問でも大歓迎です。
お気軽に下記からご連絡くださいね。