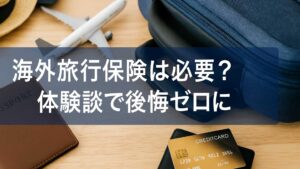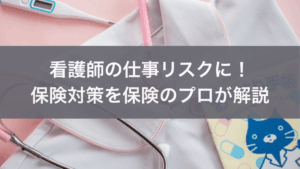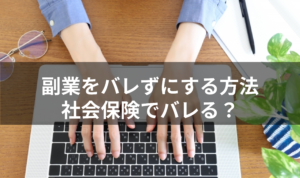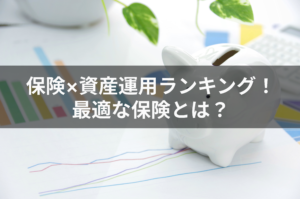「このつらい体の痛み、整体で保険を使って少しでも安くならないかな…」
あなたも一度はそう考えたことがありませんか?
でも、「整体と整骨院って何が違うの?」「私のこの症状は保険が使えるの?」と、いざという時に迷ってしまいますよね。
実は、その違いを知らないままだと、本来は数百円で済んだはずの治療費を、全額自己負担して何千円も支払ってしまうかもしれません。
この記事では、保険が使えるケースと使えないケースの明確な境界線から、具体的な料金、あなたの症状に合った最適な選び方までを徹底解説!
もう迷わせません。
無駄な出費を抑えて、賢く体をケアする方法を身につけましょう。

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
結論:残念ながら整体は保険適用外!でも諦めないでください

「つらい体の不調、整体で保険を使って安くならないかな?」
そう考えたことがある方も多いのではないでしょうか。
この章では、まず「なぜ整体で保険が使えないのか」という根本的な疑問にお答えし、その上で「整体の代わりに保険が使える選択肢」についてご紹介します。
- なぜ?整体で保険が使えない明確な理由
- 整体の代わりに保険が使える「整骨院・接骨院」とは
それでは一つずつ解説します。
なぜ?整体で保険が使えない明確な理由
結論として、私たちが普段利用している公的医療保険は、病気やケガの「治療」を目的とした制度だからです。
そのため、心身の癒やしやリラクゼーション、体質改善を目的とする整体は、残念ながら保険の対象外となります。
これは健康保険法という法律で定められており、保険が使えるのは「病気、ケガ、またはそれによる死亡、出産」といったケースに限られています。
つまり、明確な原因があって発生したケガや、医師が診断した病気の治療でなければ、保険は適用されないルールなのです。
デスクワークが続いて肩がパンパンに張ってしまった、というケースを考えてみましょう。
これはとてもつらい症状ですが、病気や突発的なケガではなく、日々の疲れや生活習慣が積み重なった「慢性的な不調」と見なされます。
整体院で体の歪みを整えてもらい、症状が楽になったとしても、それは保険制度上では「治療」ではなく「体のコンディションを整える行為」と判断されるため、保険適用にはなりません。
このように、整体が保険適用外なのは、そのサービス目的が公的医療保険がカバーする「治療」という範囲に含まれない、というはっきりとした理由があるためです。
整体師は民間資格。保険適用に必要な「国家資格」ではない
整体で保険が使えない二つ目の理由は、施術者の「資格」の違いです。
保険を使った施術を行うためには「国家資格」が必要ですが、整体師は「民間資格」にあたるため、保険の取り扱いが認められていません。
少し専門的な話になりますが、日本で保険を使った施術が法律で認められているのは、以下のような国家資格を持つ専門家です。
| 資格の種類 | 主な施術場所 | 保険適用の主な対象 |
| 医師 | 病院、クリニック | 病気やケガ全般 |
| 柔道整復師 | 整骨院、接骨院 | 急性のケガ(骨折、脱臼、捻挫など) |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 鍼灸院、マッサージ院 | 医師の同意がある特定の慢性疾患 |
これらの国家資格は、国が定めた教育課程を修了し、国家試験に合格した人に与えられ、一定水準以上の知識と技術が国によって保証されています。
皆さんが病院で診察を受けるとき、医師免許を持ったお医者さんが担当しますよね。
それと同じように、保険を使ってケガの治療を受ける場合は、「柔道整復師」という国家資格を持った先生がいる整骨院や接骨院に行く必要があるのです。
整体師の先生方の中にも素晴らしい技術を持つ方は大勢いらっしゃいますが、その資格はあくまでスクールや団体が認定する民間資格のため、国の制度である保険は使えない、というわけです。
施術者が持つ資格が、国が定めた「国家資格」であるかどうかが、保険を使えるかどうかの大きな分かれ目となっているのです。
法律上の位置づけの違い:整体は医療行為として認められていない
最後の理由は、法律上の位置づけです。
少し硬い話になりますが、整体は法律で定められた「医療行為」や「医業類似行為」には含まれないため、保険診療の対象とはなりません。
日本の法律(医師法)では、ケガの診断や手術、薬の処方といった「医療行為」は、医師にしか認められていません。
一方で、先ほどご紹介した「柔道整復師」や「あん摩マッサージ指圧師」などが行う施術は、「医業類似行為」として法律でその業務範囲が定められており、特定の条件下で保険の適用が認められています。
皆さんが病院で受ける診察は、まさにこの「医療行為」です。
また、整骨院で柔道整復師が捻挫の手当てをすることは「医業類似行為」にあたります。
しかし、整体院で行われる骨盤の調整や筋肉の緩和といった施術は、これらの法的な枠組みには入っていません。
あくまで健康増進やリラクゼーションを目的とした「自由診療」のサービスという位置づけになるため、保険を使うことはできないのです。
このように、法律で「医療」の範囲が厳密に定められていることが、整体で保険が使えない根本的な理由となっています。
整体の代わりに保険が使える「整骨院・接骨院」とは
「じゃあ、保険を使って体のケアをしたい時はどうすればいいの?」と思いますよね。
その答えが「整骨院・接骨院」です。
ここでは、「柔道整復師」という国家資格を持った専門家が施術を行っています。
「整骨院」と「接骨院」、名前は違いますが、どちらも柔道整復師が施術を行う施設で役割は全く同じです。
「ほねつぎ」という看板を見かけたことがあるかもしれませんが、これも整骨院・接骨院の昔ながらの呼び方ですね。
柔道整復師は、大学や専門学校で3年以上、骨・関節・筋肉・靭帯といった体に関する専門知識と技術を学び、国家試験に合格した体のプロフェッショナルです。
整体院がリラクゼーションや慢性的な不調の改善を主な目的とするのに対し、整骨院・接骨院はケガの治療を専門とする場所である、と覚えておくと分かりやすいでしょう。
保険を使って専門的な施術を受けたい場合は、この「柔道整復師」という国家資格者がいる「整骨院・接骨院」を選ぶ必要があるのです。
骨折・脱臼・捻挫・打撲といった「急なケガ」の治療が専門
整骨院・接骨院が専門としているのは、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)といった「急性のケガ」の治療です。
保険が適用されるのも、これらのケガに限られます。
ここで最も重要なポイントは「急性のケガ」という点です。これはつまり、「いつ、どこで、何をして痛めたか」というはっきりとした原因がある、突発的なケガを指します。
- 捻挫: 道でつまずいて足首をひねってしまった。
- ぎっくり腰: 重い物を持ち上げようとして急に腰が痛くなった。
- 打撲: タンスの角に太ももを強くぶつけてしまった。
- 挫傷(肉離れ): スポーツ中にふくらはぎの筋肉がブチッという感覚と共に痛くなった。
こうした突発的なアクシデントによるケガに対して、柔道整復師は手術や薬を使わない方法(手技療法や物理療法)で回復を促す施術を行います。
ただし、骨折や脱臼については、応急手当を除き、施術を継続するには医師の同意が必要となりますのでご注意ください。
逆に、長年の悩みである慢性的な肩こりや、原因がはっきりしない腰の重だるさといった症状は、残念ながら保険適用の対象外となります。
医師ではないため、レントゲンや薬の処方はできない
整骨院・接骨院の柔道整復師はケガ治療の専門家ですが、医師ではないという点も正しく理解しておく必要があります。
そのため、病院のようにレントゲン検査で骨の状態を確認したり、痛み止めの薬や湿布を処方したりすることは法律で禁じられています。
柔道整復師の役割は、あくまでケガをした部位に対して、手術や投薬といった医療行為によらない方法で回復を促す「施術」を行うことです。
患者さんの話を聞き、体に触れたり動かしたりしながら状態を判断し、手技療法や電気治療器などを用いた施術で治療を進めていきます。
「転んで強く手をついたけど、骨は折れていないか心配…」といった場合や、薬を飲まないと耐えられないほどの強い痛みがある場合は、まず整形外科などの医療機関を受診するのが適切です。
多くの整骨院・接骨院では、「この症状は医師の診断が必要だ」と判断した場合、提携する病院を紹介してくれます。
整骨院・接骨院は、急なケガの際に保険を使って頼れる場所ですが、医師とは役割が違うことを理解し、ご自身の症状に応じて病院と賢く使い分けることが大切です。
整骨院・接骨院なら全部OK?保険が使えない症状は?

「整骨院・接骨院なら、どんな症状でも保険が使えるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、整骨院・接骨院で保険が使えるかどうかは「症状」によって明確に分けられています。
この章では、保険が使えない症状や交通事故や労災の場合はどうなるのかを解説していきます。
- 要注意!慢性的な肩こりや腰痛は保険適用外
- 交通事故や労災の場合はどうなるの?
それでは一つずつ解説します。
要注意!慢性的な肩こりや腰痛は保険適用外
いつから始まったか分からないような慢性的な肩こりや腰痛は、整骨院・接骨院では保険適用の対象外となります。
健康保険が適用されるのは、あくまで「いつ・どこで・何をして痛めたか」が明確な「急性のケガ」に限られるからです。
長年のデスクワークによる肩のこりや、加齢に伴う腰の重だるさなどは、原因がはっきりしたケガとは見なされず、「慢性的な症状」と判断されます。
「もう何年も前から肩こりがひどくて、最近は頭痛もする…」といったお悩みは非常につらいものですが、これは急なケガではないため、整骨院で保険を使って施術を受けることはできません。
ただし、整骨院によっては、こうした慢性症状に対応するための自費診療(保険外)メニューを用意している場合があります。
ポイントは「急なケガかどうか」です。
「昨日重いものを持ち上げてから腰が痛い」なら保険適用、「ずっと前から腰が重だるい」なら保険適用外、と覚えておくと良いでしょう。
スポーツなどによる全身の筋肉疲労
特定の部位のケガではなく、スポーツ後の単なる筋肉疲労や全身の倦怠感を回復させるための施術は、保険の対象にはなりません。
これは、筋肉疲労が「ケガ」ではなく、運動によって起こる体の正常な反応と見なされるためです。
健康保険はあくまで病気やケガの「治療」を目的としているため、疲労回復やコンディショニング目的の利用は認められていません。
週末にマラソン大会を完走した後、全身がひどい筋肉痛に見舞われました。
この疲労を少しでも早く抜くために整骨院でマッサージを受けても、それは「治療」ではなく「コンディショニング」や「慰安」と判断されるため、保険は使えず自費での支払いとなります。
このように、ケガの治療ではなく、疲労回復やパフォーマンス向上を目的とした体のケアは、保険適用外となることを覚えておきましょう。
交通事故や労災の場合はどうなるの?
交通事故によるケガ(むち打ち、打撲、捻挫など)の治療は、健康保険ではなく、原則として加害者が加入している「自賠責保険」が適用されます。
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済することを目的とした、車やバイクの所有者全員に加入が義務付けられている強制保険です。
この保険から治療費などが支払われるため、被害者は整骨院の窓口で治療費を支払う必要がありません(原則自己負担0円)。
信号待ちで停車中に後ろから車に追突され、首を痛めてしまいました。
この場合、整骨院に通う際の治療費は、相手方の自賠責保険会社に直接請求されます。
そのため、受付で「交通事故です」と伝え、保険会社名と担当者の連絡先を伝えれば、窓口でのお金のやり取りは発生しません。
交通事故に遭ってしまった場合は、健康保険証ではなく、加害者の保険情報を持って整骨院に行く、と覚えておきましょう。
仕事中や通勤中のケガの場合:「労災保険」が適用される
仕事中や会社への通勤途中にケガをした場合は、健康保険ではなく**「労災保険(労働者災害補償保険)」**の対象となります。
労災保険は、事業主に雇用されて働く労働者を保護するための国の制度です。
業務上または通勤中のケガに対して、治療費などが給付されます。
こちらも、労災保険が適用されれば、窓口での自己負担は原則0円です。
会社の倉庫で重い荷物を運んでいる最中に、ぎっくり腰になってしまいました。
これは業務中に発生したケガなので、労災保険を使って整骨院で治療を受けることができます。
会社に報告して必要な書類をもらい、それを整骨院に提出することで、自己負担なく施術が受けられます。
仕事中や通勤中のケガで整骨院にかかる際は、健康保険証は使えません。まずは会社に報告し、労災の手続きを進めることが重要です。
保険を使って整骨院・接骨院の施術を受けるためのステップ

「ケガをしちゃった!整骨院に行きたいけど、どうすれば保険を使えるの?」
いざという時、スムーズに保険を使って施術を受けるための具体的な流れを、解説します。
この通りに進めれば、初めての方でも安心して利用できますよ。
- どう伝えればいい?ケガの原因や日時を正確に申告
- 施術前に必ず確認!保険適用範囲と料金
それでは一つずつ解説します。
どう伝えればいい?ケガの原因や日時を正確に申告
保険が使えるかどうかを判断する上で最も重要なのが、「負傷原因」です。
施術者にケガの状況を伝える際は、「いつ、どこで、何をして、どのように痛めたか」を具体的に申告しましょう。
なぜなら、整骨院・接骨院での保険適用は「原因がはっきりした急性のケガ」に限られているからです。
曖昧な伝え方をしてしまうと、慢性的な症状と判断されてしまい、保険が使えない可能性があります。
「なんだか腰が痛くて…」という伝え方では、原因がはっきりしません。
しかし、「昨日の夕方、自宅の庭で重い植木鉢を持ち上げようとした瞬間に、腰にグキッという痛みが走りました」と伝えれば、柔道整復師は「急性腰痛症(ぎっくり腰)ですね」と判断し、保険を適用して治療を始めることができます。
このように、負傷原因を具体的に伝えることが、保険適用の可否を分ける大切なポイントになるのです。
他の病院や整骨院で同じケガの治療を受けていないか確認される理由
問診の際に、「このケガで、他の病院や整骨院にかかっていますか?」と質問されることがあります。
これは、保険の二重請求(同じケガについて、複数の医療機関が同時に保険請求すること)を防ぐための重要な確認です。
同じケガに対して、整形外科と整骨院の両方から保険請求が上がると、それは不正請求と見なされてしまう可能性があります。
もし他の医療機関にもかかっている場合は、正直にその旨を伝えましょう。
数日前に捻挫した足首の痛みが引かないため、まず整形外科でレントゲンを撮ってもらい、湿布を処方されました。
しかし、もっと積極的に治療したくて整骨院にも行くことに。
その際、「先日、同じ足で整形外科にも行きました」と正直に伝えたところ、整骨院側で保険請求の時期を調整するなど適切に対応してくれ、何の問題もなく施術を受けることができました。
正直に申告することは、あなた自身と整骨院・接骨院を無用なトラブルから守ることにつながります。
施術前に必ず確認!保険適用範囲と料金
最も大切なことは、施術が始まる前に「今日の施術は、どこからどこまでが保険適用になりますか?」と勇気を出して質問することです。
整骨院・接骨院によっては、保険適用の施術に加えて、より高い効果を目指すための保険適用外の「自費診療」を組み合わせることを提案される場合があります。
その境界線を知らないままだと、会計時に予想外の金額を請求されて驚くことになりかねません。
ぎっくり腰の治療で整骨院にかかった際、「保険適用の施術に加えて、根本的な改善のために骨盤矯正(自費診療)もおすすめですが、いかがなさいますか?」と提案されました。
そこで、「保険が使えるのはどの施術までで、自費の矯正はいくらですか?」と確認。
先生から「電気治療と腰周りの手技までが保険適用です。骨盤矯正は別途3,000円かかります。」
と明確な説明があったため、納得した上で両方の施術をお願いすることができました。
お金のことは少し聞きにくいと感じるかもしれませんが、クリアにしておくことがお互いの信頼関係につながります。
遠慮せずに必ず確認しましょう。
保険外の自費診療を勧められた場合の判断ポイント
自費診療を勧められた際は、その施術の必要性と料金に自身が納得できるかどうかで判断しましょう。
無理に受ける必要は全くありません。
自費診療には、特殊な電気治療器を使ったり、時間をかけて全身のバランスを整えたりと、早期回復や再発予防に有効なものも多くあります。
しかし、あくまでもプラスアルファの選択肢です。
捻挫の治療で、「この特殊な電気治療器(自費)を使うと、腫れや痛みが早く引く効果が期待できます」と提案されました。
その場で「少し考えさせてください」と伝え、一度は保険適用の施術だけをお願いしました。
しかし、次の大会までに何とか間に合わせたいという気持ちが強かったため、次回の来院時に「やはり自費の治療もお願いします」と自分から申し出ました。
先生からの説明をよく聞き、その施術が自分の目的(早く治したい、根本から改善したいなど)や予算に合っているかを冷静に考えて決めることが大切です。
実際いくらかかる?保険を使った場合の料金の目安

「保険が使えるのはわかったけど、結局、窓口でいくら払うの?」というのが、皆さんが一番気になるところですよね。
この章では、整骨院・接骨院で保険を使った場合の具体的な料金について、分かりやすく解説していきます。
料金の仕組みがわかれば、安心して通院できますよ。
- 自己負担割合(1〜3割)による料金の違い
- 初診と2回目以降の料金相場
それでは一つずつ解説します。
あなたの負担割合は?年齢や所得で決まる自己負担率の基本
あなたが窓口で支払う金額の割合、つまり自己負担率は、年齢や所得によって1割・2割・3割のいずれかに決まっています。
これは健康保険法という法律で定められている全国共通のルールです。
基本的には、小学校に入学してから70歳になるまでは「3割負担」となります。
つまり、全体の治療費が1,000円だった場合、窓口で支払うのは300円、ということですね。
40代の会社員の方が、草野球で足を捻挫して整骨院にかかったとします。
この場合、年齢は70歳未満なので、自己負担割合は「3割」となります。
全体の施術料金が4,000円だったとしたら、窓口での支払いはその3割にあたる1,200円です。
ご自身の負担割合が何割かは、お持ちの健康保険証に必ず記載されています。
一度確認しておくと、料金のイメージがつきやすくなりますよ。
【一覧表】3割・2割・1割負担、それぞれの対象者
自己負担割合の対象者を、より分かりやすく一覧表にまとめました。
ご自身がどこに当てはまるか、チェックしてみてください。
| 自己負担割合 | 対象者 |
| 3割 | ・義務教育就学後~70歳未満の方・70歳~74歳で現役並み所得のある方 |
| 2割 | ・義務教育就学前の方・70歳~74歳の方(現役並み所得者を除く)・75歳以上の方(一定以上の所得がある方) |
| 1割 | ・75歳以上の方(2割負担、3割負担の条件に当てはまらない方) |
※自治体の子ども医療費助成制度などにより、窓口負担がさらに軽減される場合があります。
72歳のお父さんと、その息子で会社員の45歳の方が、同じ日にそれぞれ別のケガで整骨院にかかりました。
息子さんの自己負担割合は3割ですが、お父さんは70歳以上で現役並み所得者ではないため、負担割合は2割です。
同じような施術内容でも、窓口で支払う金額の割合が変わってくるのです。
このように、年齢や所得によって負担割合は異なります。ご家族でかかる際などは、この表を参考にしてみてください。
知っておきたい!施術する部位の数によっても料金は変動する
窓口で支払う料金は、自己負担割合だけでなく、施術する「部位の数」によっても変動することを覚えておきましょう。
整骨院・接骨院の保険施術の料金は、国によって細かく定められています。
その計算の基礎となるのが「施術した部位の数」です。
例えば「右手首」だけなら1部位、「右手首と左肩」なら2部位となり、部位数が増えるほど料金は高くなります。
自転車で転んでしまい、右手首だけを痛めたAさん。
一方で、同じく転倒したBさんは、右肩と左膝の2カ所を同時に痛めてしまいました。
この場合、施術部位が2カ所あるBさんの方が、1カ所だけのAさんよりも窓口で支払う料金は高くなります。
痛めた箇所が複数ある場合は、その分料金も高くなるのが基本ルールです。
もし料金について疑問があれば、「今日は何部位の治療になりますか?」と質問してみると良いでしょう。
初診と2回目以降の料金相場
初めて整骨院・接骨院にかかった時の料金が2回目以降より高くなるのは、「初検料(しょけんりょう)」という料金が加算されるためです。
初検料とは、いわば病院の「初診料」のようなものです。
初めてそのケガについて診察する際に、ケガの状態を詳しく見たり、検査をしたり、今後の治療方針を判断したりするための料金として、国によって定められています。
初めて整骨院を訪れた際、問診でケガの状況を詳しく聞かれ、痛む箇所を動かしたり押したりしながら丁寧に状態をチェックしてもらいました。
会計の時に料金の内訳を見ると「初検料」という項目があり、先生から「初回だけかかる料金ですよ」と説明を受けて納得。2回目からはこの料金はかからないと知り、安心しました。
初回だけ料金が高くなるのは、あなたの体の状態を正確に把握するための、いわば大切な初期投資です。
理由がわかっていれば、安心して施術を受けられますね。
【料金の目安】初診の場合(3割負担で1,000円~1,500円程度)
具体的な料金の目安として、3割負担の方の場合、初回の窓口支払いは1,000円~1,500円程度になることが多いです。
この金額は、先ほどの「初検料」に加えて、実際の施術にかかる「施術料」(1~2部位程度を想定)や、電気治療などを行った場合の「物理療法料」などが含まれた、おおよその合計額です。
朝、顔を洗おうとしてぎっくり腰になってしまい、初めて整骨院へ。
保険証を出すと、自己負担は3割とのこと。問診と検査の後、電気治療と手技による施術を受けました。
窓口での支払いは1,300円ほどで、「病院に行くのとあまり変わらないな」と感じ、思ったより安く済んでホッとしました。
もちろんケガの状態によって多少の変動はありますが、この金額を一つの目安として覚えておくと、初めて整骨院にかかる際の不安が和らぐのではないでしょうか。
【料金の目安】2回目以降の場合(3割負担で500円~1,000円程度)
2回目以降の通院では初検料がかからないため、料金はぐっと下がります。3割負担の方の場合、窓口での支払いは500円~1,000円程度が目安となります。
2回目以降の料金の内訳は、「再検料」や、施術に対する「後療料(こうりょうりょう)」、そして電気治療などの「物理療法料」などが中心となります。
初検料がない分、通いやすい料金設定になっているのです。
ぎっくり腰の治療で2回目の通院をした際、前回と同じような施術内容でしたが、会計は600円でした。
「初回よりだいぶ安いですね」と尋ねると、「2回目以降はこのくらいの料金ですよ」と教えてもらい、これなら無理なく通院を続けられると感じました。
定期的な通院が必要な場合でも、2回目以降の料金の目安が分かっていれば、経済的な計画も立てやすくなりますね。
結局どっちに行けばいい?症状別・目的別の選び方

ここまで「整骨院・接骨院」と「整体」の違いについて解説してきましたが、「じゃあ、私のこの症状はどっちに行けばいいの?」と迷ってしまう方もいらっしゃると思います。
この最後の章では、あなたの症状や目的に合わせて、どちらを選べば良いのかを判断するための、具体的なガイドラインを示します。
この使い分けを知っておけば、もう迷うことはありません。
- 急な痛みやケガの治療なら「整骨院・接骨院」
- 慢性的な不調の改善や体のメンテナンスなら「整体」
それでは一つずつ解説します。
急な痛みやケガの治療なら「整骨院・接骨院」
もしあなたの症状が「急な痛み」や「はっきりとした原因のあるケガ」なら、迷わず「整骨院・接骨院」を選びましょう。
「いつ、どこで、何をして痛めたか」が明確な急性のケガは、整骨院・接骨院の専門分野です。
これは、整骨院・接骨院にいる「柔道整復師」が、まさに骨・関節・筋肉などの急なケガ(外傷)を治療する専門家だからです。
保険が適用されるのも、これらの症状に限られます。
- 朝起きたら首が回らず、激しい痛みが走る「寝違え」
- 重い荷物を持ち上げた瞬間に腰に激痛が走った「ぎっくり腰」
- スポーツ中に相手と接触して肩や膝をひねった「捻挫」
- タンスの角に足をぶつけてひどく腫れてしまった「打撲」
- ボールを追いかけてダッシュした際に太もも裏が痛くなった「肉離れ」
これらのように、日常生活やスポーツで発生した突発的なアクシデントによる痛みは、整骨院・接骨院が最も得意とする領域です。
注意点:まずは整形外科を受診した方が良いケースとは?
整骨院・接骨院はケガ治療の頼れる味方ですが、症状によっては、まず整形外科(病院)を受診すべきケースもあります。
柔道整復師は医師ではないため、レントゲンやMRIといった画像診断、手術、薬の処方などの「医療行為」はできません。
そのため、より精密な検査や医師の診断が必要な場合は、整形外科が適切な選択となります。
- 転倒して腕が明らかに曲がっている、激痛で全く動かせない(骨折・脱臼の可能性が高い)
- 足の痛みに加えて、しびれや麻痺がある(神経損傷の疑い)
- 切り傷や出血を伴うケガ(外科的な処置が必要)
- 痛みが長期間(2週間以上)続いている、または悪化している
上記のような場合は、まず整形外科を受診し、医師の正確な診断を受けることを強くお勧めします。
その上で、医師の同意を得て整骨院・接骨院でのリハビリに移行するのが、最も安全で効果的な流れです。
よくある質問(Q&A)
Q1. 結局のところ、整体で保険は使えますか?
A1.
いいえ、残念ながら整体では健康保険は一切使えません。
整体は、リラクゼーションや体のバランスを整えることを目的としており、国の定める「治療」には当たらないためです。
また、整体師は民間資格であり、保険の取り扱いに必要な「柔道整復師」などの国家資格とは異なります。
ただし、整骨院・接骨院であれば、「ぎっくり腰」や「捻挫」といった急なケガに限り、保険を使って治療を受けることが可能です。
Q2. しつこい肩こりに悩んでいます。整骨院に行けば保険は使えますか?
A2.
原因によって異なりますが、「いつからか分からない慢性的な肩こり」の場合は、保険適用外となります。
保険が使えるのは、あくまで「いつ、どこで、どう痛めたか」がはっきりしている急なケガのみだからです。
ただし、以下のようなケースでは保険が使える可能性があります。
- 「朝起きたら首から肩にかけて激痛が走り、首が回らない」(寝違え)
- 「子どもを抱き上げた瞬間に、肩をひねって痛めた」
長年のつらい肩こりを根本から改善したい場合は、保険適用外の整体で全身のバランスを整えてもらうのがおすすめです。
Q3. 整骨院の料金は毎回だいたい同じくらいですか?
A3.
いいえ、初めてかかった日(初診)は、2回目以降よりも料金が高くなります。
これは、初診時に「初検料(しょけんりょう)」という、ケガの状態を詳しく診察するための料金が加算されるためです。
3割負担の方の場合、初回は1,000円~1,500円程度、2回目以降は500円~1,000円程度が目安となります。
また、痛めている部位の数(1カ所か2カ所かなど)によっても料金は変わりますので、毎回必ず同じ金額になるとは限りません。
まとめ
体の痛みや不調、保険を使って安くしたいと思いますよね。
しかし残念ながら、リラクゼーションや体質改善を目的とする整体は保険適用外です。
でも諦めないでください!
国家資格者がいる「整骨院・接骨院」なら、ぎっくり腰や寝違え、捻挫といった「原因がはっきりした急なケガ」に限り、保険を使って治療が受けられます。
「長引く肩こりや姿勢改善は整体」「急な痛みは整骨院」というように、あなたの目的や症状に合わせて賢く使い分けることが、つらい悩みを解決する一番の近道ですよ。
保険について気軽に相談したい方、見積もりを試してみたい方は、どんな小さな疑問でも大歓迎です。
お気軽に下記からご相談くださいね。